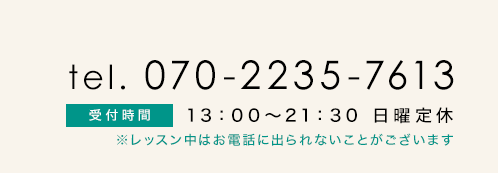動的安定性を生み出す4つのメカニズム
🏃 動的安定性とは?
「安定」というと“動かないこと”をイメージする方が多いかもしれません。
しかしスポーツの現場で求められるのは、動きの中で崩れない安定性=動的安定性です。
👉 走る・跳ぶ・投げる・方向転換といった動作を行うとき、体は常に外力を受けます。その中で姿勢をコントロールできることが、パフォーマンスとケガ予防の両方につながります。
🧩 動的安定性を生み出す4つのメカニズム
① 構造的メカニズム(Form Closure)
-
骨や関節そのものの形状が安定性を担保する仕組み。
-
例:股関節の球関節構造、足関節の距骨と脛骨の噛み合わせ。
👉 野球の投球で股関節がハマっていれば、腰や膝の負担を軽減。
② 機能的メカニズム(Force Closure)
-
筋肉・靭帯・筋膜が関節を押さえ込み、安定させる仕組み。
-
例:骨盤帯を支える殿筋群や腹斜筋群。
👉 サッカーのシュートで軸足がブレず、強いキックが可能に。
③ 神経制御(Neuromuscular Control)
-
中枢神経と末梢神経の協調により、関節や姿勢を瞬時に調整。
-
例:前庭系・固有受容感覚・視覚情報の統合。
👉 陸上短距離のスタートで接地直後に崩れないのは、この神経制御のおかげ。
④ 動的フィードバック(Feedforward & Feedback)
-
事前に予測して体を固める(Feedforward)と、動作中に修正する(Feedback)の両輪。
-
例:投球でリリース前に体幹を固め、着地時に微調整する。
👉 テニスのサーブやバスケのジャンプシュートでの安定性はこの両方が重要。
⚽ スポーツ現場での具体例
-
野球:股関節・肩甲帯の安定性がフォーム全体の再現性を高める。
-
サッカー:軸足の安定があるからこそ強いシュートや素早い切り返しが可能。
-
陸上:接地で崩れずに力を推進に変えられることが記録を伸ばす鍵。
-
テニス:肩甲帯の動的安定がないとサーブで肩を痛めやすい。
-
バスケット:着地で膝が安定しないと前十字靭帯損傷のリスクが高まる。
👪 保護者の方へ
「うちの子は体幹が弱いから不安定」という相談をよく受けます。
でも安定性は“腹筋の強さ”だけではありません。
👉 骨・筋肉・神経・感覚が連携してはじめて、動作中に崩れない「動的安定性」が身につきます。
練習の中でこの4つの仕組みを意識することで、ケガを防ぎつつ大きな成長につながります。
✅ まとめ
-
動的安定性=「動きながら安定する力」
-
4つのメカニズムで成り立つ:
①構造(Form Closure)
②機能(Force Closure)
③神経制御(Neuromuscular Control)
④フィードフォワード&フィードバック -
野球・サッカー・陸上・テニス・バスケすべてに関係する
-
強さとケガ予防の両立に欠かせない
👉 PHYSICAL MONSTER ACADEMY では、BPA-CPSに基づき、動的安定性を育てるトレーニングを実践しています。
タグ: ケガ予防, テニス, サッカー, 野球, 陸上, バスケ, シュート, パフォーマンス, 子供, ケガ, 体幹, スポーツ