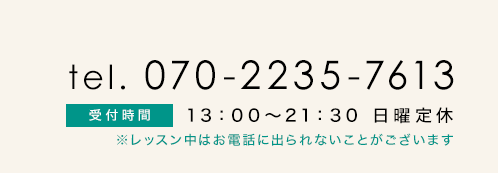反復練習は本当に正しい? ― 『反復のない反復』の考え方
🏃 はじめに
「とにかく同じ動きを100回練習すれば上達する」
そう信じている方は多いと思います。
しかし最新のスポーツ科学では、この考え方は必ずしも正しくないことが分かってきました。
キーワードは 「反復のない反復」 です。
🔑 『反復のない反復』とは?
ロシアの生理学者 N.A. Bernstein が提唱した運動制御の大問題 ― 自由度の問題と文脈上の変動性。
彼の考えを基にした概念が「反復のない反復」です。
-
同じ動作をしているつもりでも、毎回少しずつ違う
-
歩行ですら、日によって91〜95%異なるパターンが観測される
-
その差は「疲労・感情・環境」などによって生まれる
👉 つまり、「全く同じ動作」は存在せず、常に微妙な違いがあるのです。
🧩 子どもの成長にどう関わるのか?
-
環境適応力が高まる
毎回少し違う動作を経験することで、脳と体は「誤差を修正する力」を獲得。 -
ケガ予防につながる
同じ動作だけを繰り返すと負担が一部に集中。変動性は分散効果を生む。 -
スキル転移が起こる
“Key Movement(核となる動作)”を中心に、他の競技や場面に応用可能。
❌ 「同じ型だけを繰り返す練習」の問題点
-
子どもが 型に縛られすぎて応用が効かなくなる
-
試合や実戦では、常に状況が変わるため「再現性のない動き」に対応できない
-
上達よりも「動きが固まる」リスクが高まる
✅ 『反復のない反復』を取り入れる方法
-
練習条件を変える
例:ボールの大きさ、投げる角度、助走距離を少しずつ変える。 -
環境を変える
例:外・室内、芝生・体育館など場所を変える。 -
課題を加える
例:「的を狙う」「相手の動きを見て投げる」など制約をつける。
➡️ ただし「外してはいけない要素(Attractor)」は残すことが重要です。
例:走動作では「ヒップロック」「上体の安定」など。
🌱 まとめ
-
同じ動きを100回繰り返すこと=上達ではない。
-
「反復のない反復」を通じて、子どもの運動神経は“応用力”として育つ。
-
保護者が意識すべきは「失敗もOK」「違ってもOK」という環境づくり。