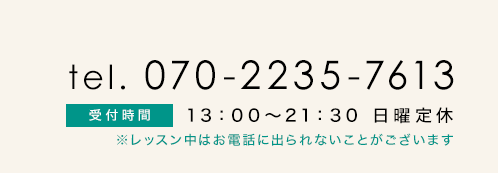練習時間が多ければ上達するはウソ? ― 自由度問題と“反復のない反復”
🏃 はじめに
「野球は1000本ノック!」「サッカーはボールを触った時間がすべて!」
「陸上は走り込みがものを言う!」
こうした“量こそ正義”の考え方は、いまだ多くのスポーツ現場で根強く残っています。
しかし、科学が示しているのはその逆。
練習量の多さ=上達ではない のです。
🔨 鍛冶屋のハンマータスク ― 同じ動きは存在しない
ロシアの生理学者ベルンシュタインは、鍛冶屋が鉄を打つ動きを詳細に計測しました。
すると驚くべきことに、同じ動きをしているように見えて、毎回違う軌道を描いていた のです。
これは「同じ動作を完璧にコピーすること」は人間には不可能であり、むしろ 揺らぎ(variability)を含んだ動作こそが自然で効率的 であることを示しています。
🧩 自由度問題とは?
人間の身体は無数の関節・筋肉・神経から成り立ち、理論上はほぼ無限の動作パターンを生み出せます。
この複雑さを「どうやって一つの動きにまとめているのか?」という疑問を 自由度問題(Bernstein’s Problem) と呼びます。
-
野球の投球 → 肩だけでなく股関節・体幹まで無数の組み合わせ
-
サッカーのドリブル → 相手DFやピッチ状況で毎回違う動き
-
テニスのサーブ → 風やボールの回転条件で同じ再現は不可能
つまり「同じ動きを何度も繰り返させる練習」自体が、現実には成立しないのです。
🌍 エコロジカルアプローチと制約主導アプローチ(CLA)
心理学者Gibsonの エコロジカルアプローチ では、動作は環境との相互作用によって形づくられると考えます。
この考え方を発展させたのが 制約主導アプローチ(Constraint-Led Approach / CLA)。
-
個人(年齢・体格・体力)
-
課題(ルール・道具・目標)
-
環境(天候・相手・スペース)
これらの 制約を操作することで、選手自身が多様な動きを自己組織化していく という理論です。
🎲 ディファレンシャルラーニング(DL) ― 反復のない反復
CLAとよく並んで語られるのが ディファレンシャルラーニング(Differential Learning)。
こちらは「揺らぎを意図的に増やす」アプローチです。
-
野球 → 足幅を変える、体をひねって投げる、ジャンプして投げる
-
サッカー → 逆足・ジャンプシュート・わざと不安定な姿勢から打つ
-
陸上短距離 → 坂道・砂場・追いかけ競争など多様なスタート
同じ結果を得るために、あえて毎回違う動きを経験させる。これが「反復のない反復」です。
💡 筋活動の多様性が成功を生む
多様性の重要性は、実際の研究でも証明されています。
-
バスケットボールのフリースロー
成功率の高い選手ほど、肩や肘、手首の 筋活動に多様性 が見られ、毎回微妙に異なる調整をしていることが分かっています。 -
デッドリフトやスクワットで腰痛にならない人
脊柱起立筋の筋活動を調べると、一定のパターンに固定されず、多様な発火パターン を持っていることが報告されています。
👉 特定の部位に負担が集中せず、ケガ予防につながる。
つまり「動作のコピー」ではなく「動作のバリエーション」が、成功と安全を保証しているのです。
👪 保護者の方へ
「たくさん練習させれば上達する」と思いがちですが、
実際には 多様な動きの中から自分なりの解決策を見つけること が大切です。
お子さまに必要なのは「やらされる反復」ではなく、環境や課題から自然に導かれる多様な練習です。
✅ まとめ
-
鍛冶屋のハンマータスク → 同じ動きは存在せず、揺らぎが自然
-
自由度問題 → 人体は複雑すぎて単純なコピー練習では適応できない
-
エコロジカルアプローチ → 環境との相互作用が動作を規定
-
CLA → 制約を操作して自己組織化を促す
-
ディファレンシャルラーニング → 反復のない反復で多様性を引き出す
-
筋活動の研究 → 成功する選手やケガをしない選手ほど、多様性を持っている
👉 結論:練習時間の多さではなく、多様な解決方法を身につけることが上達の鍵。
PHYSICAL MONSTER ACADEMY では、科学に基づいた「非線形学習×多様性のある練習」で、子どもたちの成長と安全を全力でサポートしています。
タグ: テニス, サッカー, 野球, 陸上, バスケ, シュート, トレーニング, ジャンプ, 姿勢, ケガ, アスリート, スポーツ