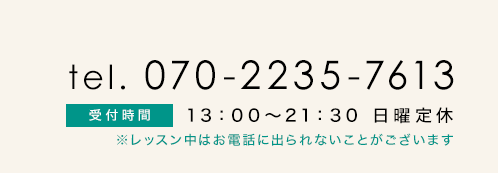🌟 自己効力感ってなに?子どもの「できる!」を育てるために大切なこと
みなさんは「自己効力感(じここうりょくかん)」という言葉をご存じですか?
ちょっとむずかしい表現ですが、これは 「ある場面で、自分はきっとやり遂げられる!」という確信 のことを指します。
よく「自己効力感=自信」と紹介されることがありますが、実は少し違います。
自信は漠然とした「できるかも」という感覚ですが、自己効力感はもっと具体的。
「跳び箱の6段を跳べる!」「逆上がりができる!」といった 特定の課題に対して“できる”と思える気持ち なんです 💡。
🏅 自己効力感を高める一番のカギは「達成体験」
心理学者バンデューラによると、自己効力感を育てるうえで一番大切なのは 達成体験(できた!という成功体験) です。
-
はじめは失敗しても、練習を重ねて「できた!」につなげる
-
小さな成功を積み重ねることで「やればできるんだ」という感覚が強くなる
これが自己効力感の土台になります。
ですから、お子さんにとっては「できないことに挑戦 → 少しずつ上達 → できた!」というステップがとても大事なんです✨。
👀 モデリング(まねして学ぶ力)
「お兄ちゃんが跳べたから、ぼくも跳べそう!」
「友だちが頑張ってるから、自分もできるかも!」
こうした 他人の成功体験を見て学ぶ(モデリング) も、自己効力感を育てる重要なポイントです。
子どもたちは身近なモデルから勇気をもらいます。
💬 言葉がけの力
「もう少しでできるよ!」「よく頑張ったね!」
コーチや親からの前向きな言葉も、自己効力感を後押しします。
逆に「なんでできないの?」といった言葉は、せっかく芽生えたやる気をしぼませてしまうことも…。
声かけはシンプルですが、とても大きな力を持っています🌱。
💓 感情や体の感じ方も関係する
試合前のドキドキを「不安だからダメかも」ととらえるか、
「よし!集中できている証拠」ととらえるかで、自己効力感は変わります。
同じ身体反応でも、ポジティブにとらえれば力になります。
親御さんが「緊張してるね、でもそれは頑張る準備ができてる証拠だよ😊」と声をかけてあげるのも効果的です。
🌱 まとめ
-
自己効力感は「自信」とは違い、特定の場面で“できる!”と思える感覚
-
一番大切なのは「達成体験」=小さな成功を積み重ねること
-
まわりのモデルや前向きな言葉がけも大きな支えになる
-
ドキドキや緊張をポジティブにとらえる工夫もポイント
お子さんが「やればできる!」と感じられる体験を積むことで、チャレンジする気持ちも伸びていきます。
その先に、スポーツだけでなく勉強や生活でも「前向きに挑戦できる力」が育っていくのです 🌈。