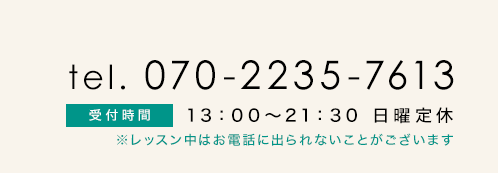🏃♂️ 習い事としてのスポーツトレーニングの価値 ― マルチスポーツが難しい日本でこそ ―
1️⃣ 「競技の前に、体の使い方を学ぶ」
スポーツトレーニングは、競技技術を教える場ではなく、あらゆる競技の基盤となる身体能力を育てる場です。
走る・跳ぶ・投げる・止まる・ひねるなどの「基本動作(Fundamental Movements)」に加え、
持久力・筋力・パワー・柔軟性・バランスといった総合的な体力要素をバランス良く高めます。
これらの能力は、どんなスポーツを選んでも共通して役立ちます。
👉 トレーニング=どんな競技にも通用する「身体能力づくり」です。
2️⃣ 「勝ち負け」よりも「成長」を実感できる
競技スポーツでは結果が基準になりますが、トレーニングは**「過去の自分より上手くできたか」**が評価軸。
この自己比較型の成長体験が、**自己効力感(self-efficacy)**を高め、主体的に行動する力を育てます。
👉 成績ではなく「成長を感じられる」場所。
3️⃣ 「姿勢・集中力・思考力」も育つ“学びの場”
運動は脳を鍛える最良の刺激です。
-
バランスを取る → 体幹と姿勢保持力の向上
-
指示を聞いて動く → 注意・集中力の向上
-
動きを改善して試す → 自己調整力(Self-Regulated Learning)
定期的なトレーニングは、学習面・生活面にも良い影響を与えます。
(参考:Hillman et al., 2008, Neuroscience)
4️⃣ 「ケガをしにくい体」をつくる
成長期の体は、骨の成長スピードに筋肉や腱が追いつかず、アンバランスになりやすい時期です。
正しいフォームと体の使い方を学ぶことで、オスグッド病・腰痛・肩痛などの障害予防につながります。
また、成長期に見られる「クラムジー(clumsy)」=一時的な不器用さも、
多様な動作経験を積むことで自然に改善されていきます。
👉 トレーニングは“未来のケガを防ぎ、動きの質を整える学び”です。
5️⃣ マルチスポーツが難しい日本では「代替」としての価値
欧米では複数のスポーツを経験する「マルチスポーツ文化」が根づいていますが、
日本では部活動やスクール制度の関係から、早期にひとつの競技に固定されがちです。
その結果、動きの多様性が失われ、偏った動作や慢性的な疲労につながることもあります。
👉 スポーツトレーニングは、
複数競技を行う代わりに多様な動作・負荷・環境刺激を体験できる場。
「動きの多様性=発育発達の土台」を確保する代替手段になります。
🔑 まとめ
習い事としてのスポーツトレーニングは、
単なる「運動教室」ではなく、
✅ 競技に縛られずに身体の土台を整える
✅ 成長を自分で実感できる
✅ マルチスポーツの代わりに多様な動きを経験できる
という、現代日本の子どもたちに必要な“第三の選択肢”です。
PHYSICAL MONSTER ACADEMYでは、科学的根拠に基づくプログラムで、子どもたちの身体と心の可能性を育てます💪
タグ: 身体能力, 跳ぶ, 投げる, 成長, 持久力, 走る, トレーニング, 姿勢, ケガ, 体幹, バランス, 柔軟性, パワー, スポーツ