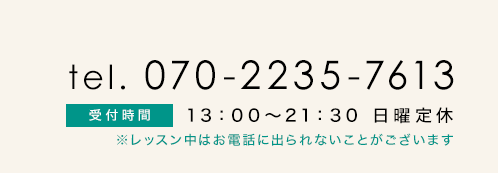反復練習は本当に正しい? ― 『反復のない反復』の考え方
🏃 はじめに
「とにかく同じ動きを100回練習すれば上達する」
そう信じている方は多いと思います。
しかし最新のスポーツ科学では、この考え方は必ずしも正しくないことが分かってきました。
キーワードは 「反復のない反復」 です。
🔑 『反復のない反復』とは?
ロシアの生理学者 N.A. Bernstein が提唱した運動制御の大問題 ― 自由度の問題と文脈上の変動性。
彼の考えを基にした概念が「反復のない反復」です。
-
同じ動作をしているつもりでも、毎回少しずつ違う
-
歩行ですら、日によって91〜95%異なるパターンが観測される
-
その差は「疲労・感情・環境」などによって生まれる
👉 つまり、「全く同じ動作」は存在せず、常に微妙な違いがあるのです。
🧩 子どもの成長にどう関わるのか?
-
環境適応力が高まる
毎回少し違う動作を経験することで、脳と体は「誤差を修正する力」を獲得。 -
ケガ予防につながる
同じ動作だけを繰り返すと負担が一部に集中。変動性は分散効果を生む。 -
スキル転移が起こる
“Key Movement(核となる動作)”を中心に、他の競技や場面に応用可能。
❌ 「同じ型だけを繰り返す練習」の問題点
-
子どもが 型に縛られすぎて応用が効かなくなる
-
試合や実戦では、常に状況が変わるため「再現性のない動き」に対応できない
-
上達よりも「動きが固まる」リスクが高まる
✅ 『反復のない反復』を取り入れる方法
-
練習条件を変える
例:ボールの大きさ、投げる角度、助走距離を少しずつ変える。 -
環境を変える
例:外・室内、芝生・体育館など場所を変える。 -
課題を加える
例:「的を狙う」「相手の動きを見て投げる」など制約をつける。
➡️ ただし「外してはいけない要素(Attractor)」は残すことが重要です。
例:走動作では「ヒップロック」「上体の安定」など。
🌱 まとめ
-
同じ動きを100回繰り返すこと=上達ではない。
-
「反復のない反復」を通じて、子どもの運動神経は“応用力”として育つ。
-
保護者が意識すべきは「失敗もOK」「違ってもOK」という環境づくり。
Bernstein問題 ― 自由度の問題と文脈上の変動性
こんにちは!
PHYSICAL MONSTER ACADEMYです。
今日はスポーツ科学の重要な理論である 「Bernstein(ベルンシュタイン)問題」 についてご紹介します。難しい学問的な内容ですが、子どものトレーニングを考える上でとても役立つ考え方ですので、できるだけわかりやすくお話しします。
自由度の問題とは?
私たちの体は、たくさんの関節や筋肉でできています。
たとえば、腕を動かすだけでも肩・肘・手首の関節があり、それぞれの関節を動かす筋肉は何十本もあります。
つまり「同じ動きをするのに、無数の組み合わせが存在する」のです。
これを 「自由度の問題(degrees of freedom problem)」 と呼びます。
例:
-
ボールを投げる → 肩の動かし方は一つではない
-
ジャンプする → 膝や足首の曲げ方は人それぞれ
この自由度の多さが、人間の動きを「難しいもの」にしているのです。
文脈上の変動性とは?
ベルンシュタインは「人間はこの自由度の問題をどう解決しているのか?」を研究しました。
その答えの一つが 「文脈上の変動性(context-conditioned variability)」 です。
簡単に言うと:
-
人の動きは毎回同じではなく、状況や文脈に応じて少しずつ変わる
-
それがむしろ「うまく対応できる力」につながっている
たとえば:
-
同じ速さで走っているつもりでも、地面の硬さや風の強さによって足のつき方は変わる
-
ボールを投げるとき、相手との距離や自分の体調によって微妙にフォームが変わる
つまり「変動は悪いことではなく、適応するために必要なこと」なのです。
子どものトレーニングにどう活かせるか?
自由度の問題と文脈上の変動性を理解すると、子どもの練習にもヒントが得られます。
-
「完璧に同じフォーム」を求めすぎないこと
少しの変動は自然なことであり、成長に必要です。 -
いろいろな環境で練習させること
違うボール、違うグラウンド、違う状況で練習することで、適応力が身につきます。 -
失敗も学びの一部と考えること
変動を経験することで「どうすればうまくいくか」を自分で学べるようになります。
PHYSICAL MONSTER ACADEMYの考え方
当アカデミーでは、子どもたちに 多様な動きと環境 を経験させることを大切にしています。
同じ動きを繰り返すのではなく、遊びやゲーム性を取り入れた練習で「自由度の問題」に対応する力を育てています。
こうすることで、試合や実戦で「思い通りに体を使える」選手へと成長していきます。
まとめ
-
自由度の問題:体の動きは無数の組み合わせがあり、複雑である
-
文脈上の変動性:動きは状況によって変わるが、それが適応力になる
-
子どもの練習では「変動を恐れず、むしろ活かす」ことが大切
スポーツだけでなく、日常生活でも「環境に応じて体を上手に使える力」が役立ちます。
その力を育むために、私たちは多様で楽しいトレーニングを提供しています。
目的によって選ぶべきトレーナーは異なる
こんにちは!
PHYSICAL MONSTER ACADEMYです。
お子さんにトレーニングを習わせたい、スポーツで活躍できる体をつくりたい――。
そんな時に必ず出てくるのが「どのトレーナーにお願いすればいいの?」という疑問です。
実はトレーナーにも、お医者さんと同じように専門分野の違いがあります。
虫歯の治療は歯医者さんに行くように、目的に合ったトレーナーに相談しないと効果が出にくいのです。
今日は、代表的なトレーナーの種類を紹介しながら、「子どもに合ったトレーナーの選び方」を一緒に考えていきましょう。
トレーナーの主な6つの種類
-
S&Cコーチ(ストレングス&コンディショニングコーチ)
アスリートの筋力・パワー・柔軟性・持久力を伸ばし、パフォーマンス向上とケガ予防を目的に指導する専門家です。 -
アスレティックトレーナー(AT)
ケガをした時に現場で対応したり、復帰までのリハビリをサポートしたりする専門家です。 -
メディカルトレーナー
理学療法士や柔道整復師など医療資格を持ち、ケガや痛みを改善し、運動機能を回復させられる専門家です。 -
フィットネストレーナー
一般の方が健康づくりや体力向上のために行う運動をサポートするトレーナーです。 -
ボディメイクトレーナー
ダイエットや理想の体型づくりを目的に、筋トレや食事のアドバイスをしてくれるトレーナーです。 -
無資格トレーナー
法律的には資格がなくても「トレーナー」を名乗ることができます。中には素晴らしい方もいますが、専門性を見極めるのが難しいのが現実です。
目的に合わせたトレーナー選びの考え方
お子さんが「スポーツで活躍したい」と思ったとき、体の状態によって相談すべき相手は変わります。
-
ケガや強い痛みがある場合 → メディカルトレーナーや病院
-
復帰途中でまだ全力プレーができない場合 → アスレティックトレーナー
-
ケガはなく、さらに能力を伸ばしたい場合 → S&Cコーチ
つまり、
-
「80しか出せていない力を100に戻す」 → 医療やATの領域
-
「100を120に伸ばす」 → S&Cコーチの領域
というイメージです。
PHYSICAL MONSTER ACADEMYができること
私たちPHYSICAL MONSTER ACADEMYは、S&Cコーチの専門領域に立ち位置を置いています。
アスリートのパフォーマンスアップを目的に、筋力・パワー・スピード・柔軟性・瞬発力などをトータルで鍛えています。
また、園児から高校生まで幅広く対応できる資格と経験を持ち、スポーツに取り組むジュニアアスリートだけでなく、運動が苦手な子どもにも「動ける体」を育む指導を行っています。
さらに、スポーツだけでなく「疲れにくい体」「集中できる体」など、日常生活のパフォーマンス向上にも役立つ内容を提供しています。
まとめ
「トレーナー=みんな同じ」ではなく、目的や体の状態によって選ぶべき専門家は異なります。
スポーツで成果を出したいなら、S&Cコーチが最適です。
もしお子さんの体づくりやパフォーマンス向上でお悩みがありましたら、ぜひPHYSICAL MONSTER ACADEMYにご相談ください!
タグ: 体, 運動, 子供, スピード, 持久力, 瞬発力, トレーニング, ケガ, 柔軟性, パワー, 筋力, アスリート, パフォーマンス向上, スポーツ
トレーニングの原理原則とは?
トレーニングには「必ず守るべき基本ルール」があります。それを トレーニングの原理原則 と呼びます。
1. 過負荷の原則
普段より少し強い刺激がないと体は成長しません。
👉 例:毎日同じ簡単な問題ばかり解いていても学力が伸びないのと同じです。
2. 漸進性の原則
負荷は少しずつ段階的に上げていく必要があります。
👉 例:いきなり難しい問題集を渡しても子どもは理解できません。レベルを少しずつ上げるからこそ力がつきます。
3. 特異性の原則
体は「与えられた刺激の種類」に応じて特異的に適応します。
👉 例:長距離走をすれば持久力がつき、重いものを持ち上げれば筋力が伸び、ジャンプやスプリントをすれば瞬発力が育ちます。やったことに応じて体が変わるのです。
4. 可逆性の原則
トレーニングをやめると効果は失われます。
👉 例:夏休みに漢字を練習して覚えても、2学期に入って書かなくなるとすぐに忘れてしまうのと同じ。
5. 個別性の原則
子どもによって体格や成長スピードは違うため、同じ練習をしても効果は一人ひとり異なります。
👉 例: 同じ風邪をひいても、すぐ治る子もいれば、長引いてしまう子もいます。体の反応や回復力も個性のひとつです。
なぜ原理原則を守ると成果が出やすいのか?
これらを無視してトレーニングとしてしまうと、
-
成長が頭打ちになる
-
ケガのリスクが高まる
-
子どもがやる気をなくす
といった問題が起きやすくなります。
逆に原理原則を守ることで、
-
無理なく、でも確実に成長できる
-
ケガを防ぎながら力を伸ばせる
-
「できた!」という成功体験が増えて自信になる
という好循環を作ることができます。
まとめ
トレーニングに魔法の近道はありません。
ですが「過負荷・漸進性・特異性・可逆性・個別性」といった 原理原則 を押さえれば、子どもは確実に成長していきます。
PHYSICAL MONSTER ACADEMYでは、この原理原則を大切にしながら、一人ひとりに合ったトレーニングを提供しています。
PHYSICAL MONSTER ACADEMYのトレーニングユニット
PHYSICAL MONSTER ACADEMYのトレーニングは、11のユニット(柱)から構成されています。それぞれのユニットが役割を持ち、順序立てて実施することで、子どもからアスリートまで安心して成長できる仕組みになっています。
11ユニットの流れ
- リセット(Reset)
身体と心をニュートラルな状態に戻す段階。呼吸や簡単な動きで、集中力を高め、トレーニングを始める準備をします。 - ブリージング(Breathing)
正しい呼吸の仕方を学ぶことで、体幹の安定・リラックス・疲労回復につなげます。 - モビリティ(Mobility)
関節の可動域を広げ、しなやかに動ける身体を育てます。ケガ予防のためにも大切なステップです。 - モーターコントロール(Motor Control)
姿勢やフォームを意識し、身体を思い通りにコントロールする力を磨きます。 - ムーブメントプレパレーション(Movement Preparation)
いわゆるウォーミングアップ。神経系や筋肉を刺激し、次のトレーニングにスムーズに入れる状態を作ります。 - ムーブメントスキル(Movement Skills)
走る・切り返す・加速するといったスポーツ特有の動きを習得します。競技力の基盤となる重要な要素です。 - プライオメトリクス(Plyometrics)
ジャンプや素早い反発動作を通じて瞬発力を高めます。爆発的なパワーを育てるトレーニングです。 - メディシンボール(Medicine Balls)
全身を使った投げ動作で、体幹や連動性を強化します。安全に全力を出す感覚を学べるステップです。 - ストレングスパワー(Strength-Power)
このユニットはさらに2つに分かれます。- トランスファー(Transfer Strength-Power)
競技動作に直結するような力の発揮を養う段階。スプリントやジャンプ、全身を連動させる動作を通して「実戦で使える力」を育てます。 - トラディショナル(Traditional Strength-Power)
バーベルやダンベルを使った従来的な筋力トレーニング。スクワットやベンチプレスのような基本動作を通して、土台となる筋力をしっかり積み上げます。
- トランスファー(Transfer Strength-Power)
- エネルギーシステムデベロップメント(ESD: Energy System Development)
持久力やスタミナを鍛え、最後までパフォーマンスを維持できる身体を育てます。 - リジェネレーション(Regeneration)
トレーニングの最後に回復を促す時間。整理運動やストレッチを行い、次の成長につなげます。
全体のつながり
これらのユニットは単独ではなく、順序立ててつなげることで最大の効果を発揮します。リセットから始まり、呼吸・動作・パワー・持久力を高め、最後にリジェネレーションで締めくくる。このサイクルを繰り返すことで、安全かつ効率的に成長できます。
まとめ
PHYSICAL MONSTER ACADEMYの11ユニットは、単なるトレーニングメニューではなく、パフォーマンス向上とケガ予防を両立する体系的な仕組みです。
専門的な知識に基づいた包括的なトレーニングメニューで子供たちの身体能力を引き上げます。
タグ: 走る, トレーニング, ジャンプ, スプリント, 連動, 姿勢, ケガ, 体幹, 柔軟性, パワー, 筋力, アスリート, パフォーマンス向上, 運動能力
パフォーマンス向上と傷害予防 ― 我々の二大ゴール
PHYSICAL MONSTER ACADEMYのトレーニングにおける二大ゴールは、パフォーマンス向上と傷害予防です。この2つは別々のものに見えますが、実際には密接に結びついており、どちらも欠かすことはできません。
パフォーマンス向上
スポーツに取り組む子どもやアスリートにとって、「より速く、より強く、より長く」動けることは競技力を高めるために不可欠です。パフォーマンス向上のためには、以下の能力を総合的に鍛えていきます:
- 筋力:動きの基盤となる力
- パワー:瞬発的に力を発揮する能力
- 持久力:長時間パフォーマンスを維持する力
- 柔軟性・可動性:スムーズに動くための関節の動きやすさ
- バランス・調整力:正確で効率的な動作を実現する能力
これらをバランスよく伸ばすことで、競技の成績だけでなく、日常生活でも「動ける身体」を手に入れることができます。
傷害予防
どれだけパフォーマンスが高くても、ケガをしてしまえばプレーを続けることはできません。スポーツ現場で多いのは、膝や足首、腰などへの繰り返しの負担から起こる傷害です。これを予防するために、
- 正しいフォームを身につける
- 体幹や関節を安定させる筋力を養う
- 過度な疲労を避け、十分な回復をとる
といった取り組みが欠かせません。傷害予防は「守り」ではなく、「継続的に成長するための土台」です。
二大ゴールは表裏一体
パフォーマンス向上と傷害予防は、決して相反するものではありません。むしろ、正しく身体を鍛えることで動きが洗練され、ケガのリスクは減ります。逆に、ケガを予防するための基礎づくりができていれば、より高いパフォーマンスに挑戦できます。
まとめ
PHYSICAL MONSTER ACADEMYが目指すのは、子どもからアスリートまで、「動ける身体」を育て、スポーツを高いレベルで長く安全に楽しめる環境を提供することです。パフォーマンスを高めながらケガを防ぐ――この二大ゴールを両立させることが、私たちの使命です。
さらに、西尾市、ひいては西三河の子どもたちが集うトレーニングの聖地となれるよう、日々精進してまいります。
タグ: 西尾市, ケガ, 体幹, 動ける身体, バランス, 柔軟性, パワー, 筋力, アスリート, 傷害予防, パフォーマンス向上, 障害予防, 運動能力, スポーツ