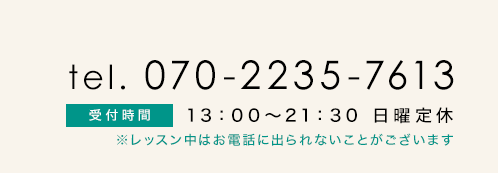レジリエンス:ストレスやプレッシャーを力に変える方法💪🌱
スポーツや勉強、日常生活の中で、子どもたちは必ず「失敗」や「プレッシャー」に直面します。
そのときに大切になるのが レジリエンス(心理的レジリエンス) です。
レジリエンスとは?🤔
レジリエンスは「逆境やストレスがあっても前に進み続ける力」を意味します。
性格や才能ではなく、トレーニングで高められるスキル であることが大きなポイントです。
🔹 困難な状況でも自分を守る力 🛡️
🔹 普段の心の働きを保ち続ける力 🧠
🔹 強みを発揮し、挑戦を続ける行動 🚀
レジリエンスが必要な場面📌
レジリエンスは、スポーツだけでなくライフスキル全般に直結します。
例えば…
💤 メンタルヘルス(不安・ストレス・睡眠)
🌪️ 失敗や挫折からの立ち直り
🔥 モチベーション(練習・試合)
🎯 目標達成・学習
🙌 自己効力感(「自分ならできる」という感覚)
子どもたちが挑戦を楽しみながら成長するために不可欠な力です✨
鍛える方法(実践のヒント)🛠️
👨👩👧👦 人との関係を大切にする
助けを求めたり、仲間と支え合うことが回復力の源になります。
🔍 自分を理解する
得意・苦手、価値観を知ることは、自信の土台となります。
✅ できたことを確認する
小さな成功を「できた!✨」と認める習慣がモチベーションを支えます。
📈 失敗を前向きにとらえる
失敗を「終わり」ではなく「次のステップ」に変える視点を持つこと。
🎯 目標を持ち、意味を見出す
「なぜ頑張るのか?」という目的意識が心を強くします。
😌 不安やイライラを自分で止める
(例)気づき → 深呼吸 → 行動を切り替える、という練習を。
🌞 楽観的に物事をとらえる
「問題」ではなく「課題」と考えるだけで心の余裕が変わります。
🌱 「まだこれから」を受け入れる
未完成でも大丈夫。「Power of Yet(まだこれから)」が成長を促します。
🔄 適応力を高める
変化を恐れず、新しい考え方や行動を取り入れること。
⏳ 長期的な視点を持つ
今の結果に一喜一憂せず、人生の大きな流れの中で成長をとらえること。
まとめ📝
レジリエンスは、生まれつきの才能ではなく 「鍛えられる力」 です。
子どもたちが失敗を恐れず、挑戦を楽しみ続けられるように、日常の中で少しずつ「心のトレーニング」を取り入れていきましょう💪🌟
子どもの「恐怖」と「痛み」の関係を知っていますか?
こんにちは!PHYSICAL MONSTER ACADEMYです😊
今日は、ちょっと専門的だけど実はとても身近なテーマ―― 「恐怖」と「痛み」 の関係についてお話しします。
💭 恐怖が行動を変える
ケガや失敗を経験した子どもは、痛みだけでなく 「また痛いかもしれない」 という恐怖心を抱きます。
この恐怖が強すぎると…
-
ケガをした足をかばって走らない
-
転ぶのが怖くてジャンプを避ける
-
「また痛くなるかも」と思ってチャレンジしない
こうした 恐怖回避行動 が増えてしまいます。
一見「安全」そうですが、実は体を動かす機会を減らし、筋力や柔軟性の低下につながることもあります。
🏃♀️ 動くのが怖い…Kinesiophobia(動作恐怖)
スポーツ医学の分野では、動くこと自体に強い恐怖を感じることを Kinesiophobia(動作恐怖) と呼びます。
研究によると、この恐怖心が強い人ほど…
-
リハビリの成果が出にくい
-
ケガからの回復が遅れる
といった影響が報告されています。
🧠 恐怖は「痛みの感じ方」まで変える
恐怖や不安は、単なる気持ちの問題ではなく 痛みの感じ方そのもの に影響します。
-
実際には冷たい刺激なのに「これはすごく熱いよ」と言われると、人は “やけどするかも” と恐怖を連想し、より強い痛みを感じてしまう 実験があります。
-
慢性腰痛の患者さんでは、恐怖心が強いと筋肉を固めすぎて歩行がぎこちなくなることがわかっています。
つまり「痛みが出るかも」という予測や恐怖が、動きや感じ方を増幅させてしまうのです。
💡 子どもの恐怖にどう向き合う?
保護者の方ができることは、とてもシンプルです。
✅ 安心させる言葉がけ
-
「大丈夫、少しずつできるよ」
-
否定せずに、前向きな言葉を選ぶ
✅ 成功体験を積ませる
-
小さな動作でも「できた!」を感じさせる
-
失敗しても励まし、チャレンジを続けさせる
✅ 正しい知識を伝える
-
「必要以上に安静にしすぎると、回復が遅れてしまうことがある」
-
「専門家の指導を受けながら、少しずつ体を動かすことがリハビリにつながる」
🌈 まとめ
子どもの「恐怖」は自然な感情ですが、強すぎると回復や成長の妨げになります。
だからこそ、保護者の温かい言葉やサポートで「怖い」から「やってみよう!」へと気持ちを切り替えられるようにしてあげることが大切です😊
PHYSICAL MONSTER ACADEMYでは、子どもたちが安心してチャレンジできる環境を整え、心と体の成長を全力でサポートしています💪✨
🌟 自己効力感ってなに?子どもの「できる!」を育てるために大切なこと
みなさんは「自己効力感(じここうりょくかん)」という言葉をご存じですか?
ちょっとむずかしい表現ですが、これは 「ある場面で、自分はきっとやり遂げられる!」という確信 のことを指します。
よく「自己効力感=自信」と紹介されることがありますが、実は少し違います。
自信は漠然とした「できるかも」という感覚ですが、自己効力感はもっと具体的。
「跳び箱の6段を跳べる!」「逆上がりができる!」といった 特定の課題に対して“できる”と思える気持ち なんです 💡。
🏅 自己効力感を高める一番のカギは「達成体験」
心理学者バンデューラによると、自己効力感を育てるうえで一番大切なのは 達成体験(できた!という成功体験) です。
-
はじめは失敗しても、練習を重ねて「できた!」につなげる
-
小さな成功を積み重ねることで「やればできるんだ」という感覚が強くなる
これが自己効力感の土台になります。
ですから、お子さんにとっては「できないことに挑戦 → 少しずつ上達 → できた!」というステップがとても大事なんです✨。
👀 モデリング(まねして学ぶ力)
「お兄ちゃんが跳べたから、ぼくも跳べそう!」
「友だちが頑張ってるから、自分もできるかも!」
こうした 他人の成功体験を見て学ぶ(モデリング) も、自己効力感を育てる重要なポイントです。
子どもたちは身近なモデルから勇気をもらいます。
💬 言葉がけの力
「もう少しでできるよ!」「よく頑張ったね!」
コーチや親からの前向きな言葉も、自己効力感を後押しします。
逆に「なんでできないの?」といった言葉は、せっかく芽生えたやる気をしぼませてしまうことも…。
声かけはシンプルですが、とても大きな力を持っています🌱。
💓 感情や体の感じ方も関係する
試合前のドキドキを「不安だからダメかも」ととらえるか、
「よし!集中できている証拠」ととらえるかで、自己効力感は変わります。
同じ身体反応でも、ポジティブにとらえれば力になります。
親御さんが「緊張してるね、でもそれは頑張る準備ができてる証拠だよ😊」と声をかけてあげるのも効果的です。
🌱 まとめ
-
自己効力感は「自信」とは違い、特定の場面で“できる!”と思える感覚
-
一番大切なのは「達成体験」=小さな成功を積み重ねること
-
まわりのモデルや前向きな言葉がけも大きな支えになる
-
ドキドキや緊張をポジティブにとらえる工夫もポイント
お子さんが「やればできる!」と感じられる体験を積むことで、チャレンジする気持ちも伸びていきます。
その先に、スポーツだけでなく勉強や生活でも「前向きに挑戦できる力」が育っていくのです 🌈。