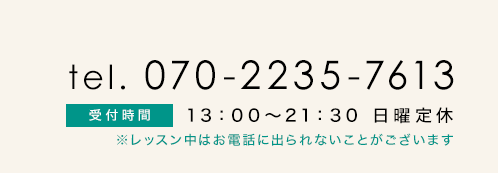🧠 Train Movement, Not Muscles ― 動作を鍛える
💡 筋肉を鍛えるより「動作」を鍛える
「トレーニング=筋肉を鍛える」と思っていませんか?
実は、身体は“筋肉単位”ではなく、“動作単位”で機能しています。
脳は「脚の筋肉」「背中の筋肉」ではなく、
「走る」「しゃがむ」「投げる」といった動作パターンで身体を制御しているのです
BPA-CFT Ver.1.1
。
だからこそ、筋肉だけを鍛えても、
実際の動きや競技でのパフォーマンスは上がりません。
必要なのは――動作そのものを整えて鍛えること。
⚙️ 動作を鍛えることで変わる3つの力
1️⃣ 姿勢・フォームを保つ力(スタビリティ)
2️⃣ 関節を自在に動かす力(モビリティ)
3️⃣ 思い通りに動かす力(モーターコントロール)
この3つが整うことで、
「効率よく力を伝えられる」「ケガをしにくい」「速く動ける」身体へと進化します。
🔁 PHYSICAL MONSTER ACADEMYのトレーニングユニット
アカデミーでは、単なる筋トレではなく、
**“動作の再教育”としてのトレーニングサイクル(11ユニット)**を実施しています。
🧩 1ユニットの流れ
Reset(リセット)
身体と心をニュートラルな状態に戻す段階。呼吸や簡単な動きで集中力を高め、トレーニングへの準備を整えます。
Breathing(ブリージング)
正しい呼吸を学び、体幹の安定・リラックス・疲労回復へとつなげます。
Mobility(モビリティ)
関節の可動域を広げ、しなやかでケガに強い身体を育てます。
Motor Control(モーターコントロール)
姿勢やフォームを意識し、身体を思い通りに操る力を磨きます。
Movement Preparation(ムーブメントプレパレーション)
いわゆるウォーミングアップ。神経や筋肉を刺激し、動きの精度を高める準備段階です。
Movement Skills(ムーブメントスキル)
走る・切り返す・加速するなど、スポーツに必要な動作を習得します。
Plyometrics(プライオメトリクス)
ジャンプや反発動作を通して瞬発力を育てます。
Medicine Balls(メディシンボール)
全身を使った投げ動作で体幹や連動性を強化。安全に全力を出す感覚を学びます。
Strength-Power(ストレングスパワー)
-
Transfer Strength-Power:実戦動作に近い動きで「使える力」を養成
-
Traditional Strength-Power:スクワットやベンチプレスなど基本的な筋力強化
ESD(Energy System Development)
スタミナや持久力を鍛え、最後まで戦える身体に。
Regeneration(リジェネレーション)
ストレッチや整理運動で回復を促し、次の成長へ備えます。
🏋️♂️ 「動ける身体」が未来の力になる
「筋トレ=重いものを持つ」ではありません。
**動作を整え、全身を連動させることこそが“本当のトレーニング”**です。
子どもたちの「走る」「跳ぶ」「投げる」力を伸ばすために、
PHYSICAL MONSTER ACADEMYでは、今日も“動作”を鍛えています。
📌 まとめ
Train Movement, Not Muscles. ― 単一の筋肉ではなく、動作を鍛える。
筋肉ではなく「動き」を変えることが、
一生使える“動ける身体”をつくる第一歩です。
🏫 PHYSICAL MONSTER ACADEMY
園児から大学生までを対象とした
スポーツパフォーマンスジム(愛知県西尾市)
📍無料体験受付中
🔖 ハッシュタグ
#フィジカルモンスターアカデミー #動作を鍛える #体幹 #運動神経 #走りの基礎 #柔道 #陸上 #サッカー #バスケットボール #野球 #バレーボール #子どものトレーニング #姿勢改善 #スポーツキッズ #愛知県西尾市 #西三河スポーツ
タグ: 運動神経, 筋肉, 柔道, バレーボール, 子ども, 筋トレ, サッカー, 野球, 陸上, バスケ, トレーニング, 連動, 姿勢, ケガ, 体幹, スポーツ
ケガのリスク=「脆弱性 × 脅威」 ― 子どもの体を守る“科学的な考え方”
⚠️ ケガは“偶然”ではない
「たまたま転んでケガしただけ」
「練習中のアクシデントだから仕方ない」
そう思われがちですが、ケガは偶然ではなく“条件がそろって起きる現象”です。
トレーニングの現場では、このケガの仕組みを数式で説明できます👇
🧠 ケガのリスク = 脆弱性(Vulnerability) × 脅威(Threat)
つまり、どちらか一方だけでなく、
「身体が弱っている(脆弱性)」と「外的な負荷(脅威)」が重なった時に
ケガは発生します。
💡 「脆弱性」と「脅威」とは?
| 要素 | 内容 | 例 |
|---|---|---|
| 🧍♂️ 脆弱性(Vulnerability) | 体の内側にある“ケガしやすさ”の要因。 | 姿勢の崩れ、筋のアンバランス、可動性不足、疲労の蓄積など。 |
| ⚡ 脅威(Threat) | 外部から加わるストレス・刺激。 | 練習量の増加、気温変化、フォームの乱れ、過度な負荷など。 |
どんなに才能があっても、
姿勢や呼吸、動作が崩れて“脆弱性”が高い状態では、
ちょっとした練習の変化(脅威)でもケガに直結します。
逆に、動きを整えて脆弱性を下げておけば、
多少の負荷がかかっても耐えられる「強い身体」になります。
⚙️ “脆弱性”を減らす=整える力を高める
ケガを防ぐ一番の方法は、「我慢」ではなく「整えること」。
PHYSICAL MONSTER ACADEMYでは、以下の3つを重視しています👇
1️⃣ 呼吸を整える
→ 体幹を安定させ、力を正しく伝える。
2️⃣ 動きを整える
→ 可動性と安定性のバランスを回復。
3️⃣ 姿勢を整える
→ 関節の位置を整え、動作のズレを修正。
これにより、「脆弱性」が下がり、
ケガをしにくい“レジリエント(回復力のある)身体”が育ちます。
🔍 「脅威」を適切にコントロールする
一方で「脅威(Threat)」はゼロにはできません。
成長期の子どもにとって、練習・試合・成長痛などは
避けて通れない負荷でもあります。
だからこそ、
📊 練習量の管理
😴 休息と睡眠の確保
🥗 栄養と回復
これらを意識して、**“脅威をコントロール”**することが重要です。
🧠 ケガを防ぐための「数式思考」
| 状態 | 結果 |
|---|---|
| 高い脆弱性 × 大きな脅威 | 🚨 ケガのリスク大 |
| 低い脆弱性 × 大きな脅威 | ⚠️ 一時的な負担だが回復可能 |
| 低い脆弱性 × 適度な脅威 | 💪 成長が加速・パフォーマンス向上 |
つまり、ケガを防ぐには――
脆弱性を下げる(整える) × 脅威を管理する(無理しない)
この両輪が欠かせません。
🏫 PHYSICAL MONSTER ACADEMYが伝えたいこと
愛知県西尾市のPHYSICAL MONSTER ACADEMYでは、
園児から大学生までを対象に、
「脆弱性を下げるトレーニング」を日々行っています。
呼吸・姿勢・動作を整え、身体を“壊れにくく、動ける”状態へ。
💬 ケガは偶然ではない。
整え方を知ることが、最大のケガ予防です。
📍#西尾市 #スポーツ教室 #子どもトレーニング #ケガ予防
#西尾市
#子どもトレーニング
#スポーツ教室
#姿勢改善
#ケガ予防
#成長期
#成長期アスリート
#野球
#サッカー
#バスケ
#バレー
#柔道
#陸上
#運動神経
タグ: 運動神経, バレー, 柔道, 子ども, サッカー, 野球, 陸上, バスケ, フォーム, 成長, トレーニング, 姿勢, ケガ, 体幹
柔軟性ではなく“可動性”を育てよう― ストレッチでは解決できない問題 ―
「カラダが硬い=ストレッチすればOK」
これは 半分正しくて半分誤りです。
ストレッチで筋肉が伸びても、
✅ 動きが改善しない
✅ 姿勢が悪いまま
✅ ケガが繰り返される
こういったケースは多くあります。
原因は👇
柔軟性(Flexibility)と可動性(Mobility)は違うからです。
🧩 柔軟性と可動性の違い
| 柔軟性(Flexibility) | 可動性(Mobility) | |
|---|---|---|
| 意味 | 他動的にどれだけ関節が動くか | 自分で関節をコントロールして動かせる能力 |
| 主役 | 筋肉の伸び、組織の柔らかさ | 神経 × 筋 × 関節の連携 |
| 例 | 他人が足を持ち上げると高く上がる | 自分で深くしゃがめる(スクワット) |
👉 動ける身体=可動性が高い身体
柔らかくても使えないと意味がないのです。
❌ 柔らかい=動ける ではない
✅ 柔軟性は十分ある
❌ でもスクワットが浅い
❌ 動きがぎこちない
❌ すぐケガをする
これは筋肉は伸びるけれど👇
“正しい順番で使えていない”サイン
✅ 可動性がなく、代償動作が起きている状態です。
例)
股関節を使えず膝・腰が代わりに頑張る → 膝痛・腰痛へ
🧠 可動性は「神経系の学習」がカギ
関節を正しく動かすには👇
-
どれだけ動けるキャパがあるか(柔軟性)
-
どう動かすか(神経制御)
この両方が必要です。
つまり…
ストレッチだけでは不十分!
➡ 脳が「正しい動き方」を学ぶ必要がある
✅ 可動性を育てるには「動作ドリル」
PHYSICAL MONSTER ACADEMYでは
以下の順番で改善します👇
1️⃣ Reset:過緊張やクセを解除
2️⃣ Breathing:肋骨と骨盤の連動を整える
3️⃣ Motor Control:正しい動作の順番を学ぶ
4️⃣ Movement Skills:スポーツ動作に応用
📌「動けない原因」を消してから、
「動きやすい身体」にアップデートします。
✅ まとめ
| 一般の考え | 本当の改善 |
|---|---|
| 柔らかければ動ける | ➜ 正しい動きができて動ける |
| ストレッチすれば解決 | ➜ 動作パターンの再学習が必要 |
| ケガ予防=柔軟性 | ➜ 可動性と制御力がセット |
📌 柔軟性は“素材”、可動性は“使い方”
柔らかいだけでは不十分。
動いてこそ意味がある柔らかさを育てましょう💪
💬 保護者の方へ
お子さんの「姿勢が崩れる」「ケガしやすい」には理由があります。
ストレッチだけでは変わらない根本を、私たちが改善します。
動ける土台が整うと、
スポーツも勉強も自信がつきます✨
📍PHYSICAL MONSTER ACADEMY(西尾市)
園児〜大学生対象のスポーツパフォーマンスセンター
子どもに筋トレは危険?🙅♂️
まだ信じられている迷信、科学的に解説します。
「筋トレすると背が伸びない」
「子どもに重いものを持たせたら危ない」
…実はこれ、昔のイメージから生まれた誤解です。
🔍現在は、国際的な研究・専門機関の結論はこう👇
👉 適切に計画・監督された筋トレは、安全で効果的!
👉 成長を妨げる根拠はない!
むしろ、体も心も成長する「やらなきゃ損」の運動なのです💪
❓なぜ「危険」という迷信が残っているのか?
昔の話 ⬇
・ケガが多いスポーツ現場で
・無理な重さを扱ってしまった例
・指導者不在の自己流筋トレ
→ これが「筋トレ=危ない」の印象に😥
📌でもこれは大前提が欠けています
▶ 専門家の指導がない状態の話
✅ 安全性について
NSCA(世界的S&C団体)の最新報告では👇
➡ 計画された筋トレのケガ率は、サッカーやバスケより低い
➡ 骨の成長を阻害した例は報告なし
➡ むしろ、骨密度アップに効果あり ✅
📌成長軟骨の損傷も、研究ではゼロ(適切な実施条件下)
安心して取り組める運動です🙆♀️🙆♂️
🎯 子どもの筋トレがもたらすメリット
| 効果カテゴリ | 期待できる変化 |
|---|---|
| 競技力向上 | 走る・跳ぶ・投げる力UP、フォーム安定 |
| ケガ予防 | 体幹・関節の安定性向上 |
| 健康 | 心肺・代謝機能改善、肥満予防 |
| メンタル | 自己肯定感UP、成功体験が積み上がる |
| 生涯スポーツ | 運動習慣につながる |
📌特に肥満傾向の子ほど
筋トレは「しんどくなく続けられる運動」として効果大◎
📈 年齢によって「やるべき筋トレ」は違う
成長段階に応じて、内容は変える必要があります👇
(LTAD:長期的アスリート育成モデル)
| 年齢 | 主体となる内容 |
|---|---|
| 6〜9歳(女の子は〜8歳目安) | ラン・ジャンプ・コーディネーション中心 |
| 9〜12歳(女子8〜11歳) | 自体重・メディシンボールなど 軽負荷導入 |
| 中学生以降 | 徐々にダンベル・バーベルも |
📌大事なのは「誰に・何を・どう教えるか」
🚫注意!やってはいけないこと
| NG行動 | 理由 |
|---|---|
| YouTubeの真似で大人の筋トレ | 身体に合わずケガの原因 |
| 重さだけを追う | 成長軟骨への負担 |
| 指導者不在 | 技術の誤りで危険UP |
✅ 正解は「専門家のもとで」
うちの子はどうしたら安全に効果が出る?
→ 資格を持ったS&C指導者へ!
(例:NSCA-CSCS / JATI-ATI)
PHYSICAL MONSTER ACADEMYでは…
✅ 発育発達を理解したプログラム
✅ 安全管理を徹底
✅ 全員の技術習得を見ながら負荷調整
安心してお任せください😊
✨まとめ
| ❌迷信 | ✅本当 |
|---|---|
| 筋トレは子どもに危険 | 正しく行えば安全で効果的 |
| 背が伸びない | 骨密度が高まりむしろ◎ |
| 大人の真似でOK | 専門家の指導必須 |
🔥子どもの未来をつくるのは
“正しい運動の積み重ね”です。
「やらせない」ではなく
「正しくやらせる」選択を😊
⚙️🧠 安定性とは筋力ではない ― 正しいタイミングが運動を変える ~「強くする」だけでなく「力発揮のタイミング」が大切~
1️⃣ 「安定=筋肉を固める」ではない
「体幹を鍛えましょう!」という言葉をよく聞きます。
でも、体幹を“固める”ことがだけが安定ではありません。
安定性(Stability)とは、
動きの中で必要な筋肉が、必要なタイミングで働くこと。
「固定する筋力」だけではなく、
「動くための制御力」なのです。
つまり、「安定性」は微調整された制御であり、
力ではないということです。
2️⃣ 筋力があっても“タイミング”がズレると崩れる
このタイミングがズレると、
どんなに筋肉が強くてもボールに力が伝わらず、フォームも不安定になります。
つまり、筋力の「量」に加え、
力を出す「タイミング」こそが安定性を生み出すのです。
3️⃣ 安定性の主役は「神経系」
筋肉を支配しているのは脳と神経。
安定性とは、筋肉が「いつ・どの順番で・どの強さで」働くかを調整する
神経の能力です。
そのため、安定性を鍛えるトレーニングでは👇
🧠 感覚(視覚・前庭・固有受容)を使う
⚙️ 小さな揺らぎやバランスの変化を体験する
🦶 足裏や体幹の“反応の速さ”を高める
など、神経系を刺激するような運動が必要になります。
4️⃣ 「固める」より「反応する」トレーニング
PHYSICAL MONSTER ACADEMYのトレーニングでは、
安定性=“静止する力”ではなく、
**“反応して戻せる力”**と捉えています。
たとえば👇
-
バランスパッド上での片足動作(揺れに反応して安定)
-
ウォーターバッグ(Aquabag)での動作(中の水が動いても姿勢を保つ)
これらは筋肉を「固める」練習ではなく、
全身を協調的に制御する練習です。
5️⃣ 「強い体」に加え「反応できる体」へ
子どもに必要なのは、筋肉量だけではなく、
**身体をどうコントロールするかという“神経的な賢さ”**です。
研究でも、安定性トレーニングは筋肥大ではなく、
運動単位の動員タイミングや反射応答の改善によって
動作の精度やバランスが向上すると報告されています
(Behm & Anderson, 2006)。
6️⃣ 家でもできる!「タイミング安定トレーニング」
✅ 目を閉じて片足立ち(5秒)
✅ 軽く押されたら姿勢を保つ(押された瞬間に反応)
✅ ペットボトルに水を入れて持ちながらスクワット
どれも“揺れ”を感じながらコントロールする練習。
固めず、反応しながらバランスを取ることを意識しましょう。
✅ まとめ
-
安定性とは「止まる力」ではなく「タイミングの力」
-
筋力の量より、動きの中での“制御”が大切
-
安定性は神経系が作り出す“動的バランス”
-
固めるのではなく、反応して戻すトレーニングを
💬 保護者の方へ
お子さんが「姿勢が悪い」「動きがぎこちない」と感じるとき、
必要なのは“筋トレ”だけではなく、
動きのリズムと協調性です。
タイミングを整えることで、
驚くほどスムーズに動けるようになります。
📍PHYSICAL MONSTER ACADEMY(フィジカルモンスターアカデミー)
愛知県西尾市熊味町上池田6番地
園児・小学生。中学生・高校生・大学生を対象としたスポーツパフォーマンスジム
タグ: 園児, タイミング, ジム, 小学生, 中学生, 大学生, 高校生, コントロール, 安定, 筋肉, 力, 筋トレ, パフォーマンス, 運動, トレーニング, 姿勢, 体幹, バランス, 筋力, スポーツ
“代償動作”とは? ― 無意識のクセがケガを呼ぶメカニズム ⚠️ ~「動けている」と「正しく動けている」は違う~
1️⃣ 「動けているのに、なぜ痛くなるの?」
子どもがスポーツをしていると、
「走れている」「投げられている」「跳べている」ように見えても、
なぜかケガを繰り返すことがあります。
その原因の多くが、**“代償動作(compensation)”**です。
2️⃣ 代償動作とは?
本来動くべき関節や筋肉がうまく働かないとき、
別の部位が代わりに動こうとすること。
それが代償動作です。
一部がサボると、別の場所が頑張りすぎる。
その負担が積み重なって、痛みや違和感として現れます。
3️⃣ ケガをしたときの「かばい動作」も代償
たとえば、
-
右足をケガしていると、左足で体重を支え続ける
-
肩が痛いとき、背中や腰を使って腕を上げる
-
ひざが痛いとき、股関節や腰をひねって代わりに動く
これらは一見「工夫して動けている」ように見えますが、
実際には他の部位が無理をして代わりに働いている状態です。
短期的には痛みを避けられますが、
その動きを続けると、別の場所に新たな負担が生まれてしまいます。
4️⃣ 人間は「正しい動き」より「楽な動き」を選ぶ
代償動作が起こるのは、身体の欠陥ではありません。
それは、脳が最も効率的に動くように指令を出しているためです。
脳はいつも「どうすれば最小限のエネルギーで目的を達成できるか」を考え、
“正しい動作”ではなく、“抵抗の少ない動作”を選ぶようにできています。
この仕組みは「最小抵抗の法則(Law of Least Resistance)」と呼ばれます。
身体はいつも、最も“楽な動き”を選ぶ。
だからこそ、間違った動きでも「動けてしまう」のです。
その「最小抵抗の動き」が続くことで、
誤った運動パターンが定着し、ケガやフォームの乱れへとつながります。
5️⃣ 無意識の“楽な動き”がクセになる
代償動作は意識せずに起こり、
いつの間にか「自分の動き方」として定着します。
-
股関節が硬い → 腰を反らせて動く
-
胸が動かない → 肩が前に出る
-
足首が硬い → 膝で吸収してしまう
このように“本来使うべき部分”が使われなくなり、
代わりの筋肉が過剰に働くことでアンバランスが進行します。
6️⃣ 代償動作を整えるには?
ただ「フォームを直す」だけでは不十分です。
重要なのは、身体が自然に“正しい順番”で動けるように再教育すること。
PHYSICAL MONSTER ACADEMYでは、
全11のトレーニングユニットを使って、代償動作を根本から整えます👇
🧩 11ユニットで「代償動作」から“自然な動き”へ
1️⃣ Reset(リセット)
身体と心をニュートラルに戻し、緊張や左右差をリセット。
2️⃣ Breathing(ブリージング)
呼吸を整え、体幹と姿勢の安定を取り戻す。
“支えの中心”を再構築するステップ。
3️⃣ Mobility(モビリティ)
動かなくなった関節を再び動かし、
使えなかった部位を“使える状態”に戻す。
4️⃣ Motor Control(モーターコントロール)
動作の順番とタイミングを再教育し、
誤った「代償ルート」を神経レベルで修正する。
5️⃣ Movement Preparation(ムーブメントプレパレーション)
神経系と筋肉を刺激し、スムーズに“再学習した動き”を呼び起こす。
6️⃣ Movement Skills(ムーブメントスキル)
走る・止まる・切り返すなどの動作の中で、全身の連動を再統合。
7️⃣ Plyometrics(プライオメトリクス)
地面反力を正しく使い、爆発的な力を出す“安定したジャンプ動作”を再構築。
8️⃣ Medicine Balls(メディシンボール)
体幹と四肢の連動を鍛え、動作中の「力の伝達」を整える。
9️⃣ Strength–Power(ストレングス・パワー)
トラディショナル(基礎筋力)とトランスファー(動作出力)で、
安定して力を発揮できる身体を作る。
🔟 ESD(エネルギーシステムデベロップメント)
疲労時でもフォームが崩れないように、持久力と集中力を養う。
1️⃣1️⃣ Regeneration(リジェネレーション)
呼吸・ストレッチ・整理運動で回復を促し、次の動作学習へ備える。
“痛みを消す”ことではなく、
“身体が本来の順番で動きを選べるようにする”こと。
それがPHYSICAL MONSTER ACADEMYの代償動作アプローチです。
✅ まとめ
-
代償動作は「使えない部分を避けて動く」自然な適応反応
-
脳は「正しい動き」より「楽な動き(最小抵抗の法則)」を選ぶ
-
その動きがクセになると、痛みやフォーム崩れの原因になる
-
PHYSICAL MONSTER ACADEMYでは、11のユニットで“自然な動き”を再教育
💬 保護者の方へ
お子さんが「痛みはないけど動きがぎこちない」とき、
それは“かばい動作”が残っているサインかもしれません。
身体全体を整えることで、
本来のスムーズでしなやかな動きが戻っていきます。
タグ: 集中力, 身体, ストレッチ, フォーム, 持久力, 走る, ジャンプ, 連動, 姿勢, ケガ, 体幹, パワー, スポーツ
ケガの原因は「痛い場所」ではない 🧩 ~身体はすべてつながっている~
1️⃣ 「痛いところ=悪いところ」とは限らない
子どもが「ひざが痛い」「腰が痛い」と言うと、
多くの人はその場所を直接ケアしようとします。
でも、スポーツのケガの多くは
「痛い場所=原因の場所」ではないのです。
たとえば、
-
ひざが痛い → 股関節や足首の動きが硬い
-
肩が痛い → 胸郭や骨盤の位置が崩れている
-
腰が痛い → 呼吸や体幹の安定性が低下している
といったように、痛みは“結果”であって、原因は別の場所にあることがほとんど。
2️⃣ 身体は「部分」ではなく「つながり」で動く
人の身体は、筋肉や骨がバラバラに働いているわけではありません。
歩く・走る・投げるなどの動作では、常に**全身が連動(連鎖)**しています。
この考え方を「運動連鎖(Kinetic Chain)」といいます。
たとえば、
-
野球の投球では「足 → 骨盤 → 胸 → 肩 → 手」の順で力が伝わる
-
サッカーのシュートでは「体幹 → 股関節 → 膝 → 足首」が連続的に働く
この流れのどこか一箇所がうまく動かないと、
他の部位が代わりに頑張り、結果的に“痛み”が出てしまうのです。
3️⃣ ケガは「代償動作」から始まる
身体のどこかがうまく機能していないと、
他の部分がその動きを“代わりにやる”ようになります。
これを**代償動作(compensation)**と呼びます。
例)
-
股関節がうまく動かない → 腰が余計に反る
-
胸が硬い → 肩で無理に動かす
-
足首が硬い → ひざにねじれが集中する
このように「一見関係なさそうな場所」が原因になり、
時間をかけて痛みが表面化してくることが多いのです。
4️⃣ 「痛みを消す」ではなく「動きを整える」
子どものケガで大切なのは、
痛みのある部位だけを休ませることではなく、
身体全体の動きを見直すことです。
痛みを一時的に抑えるだけでは、
根本の問題(動きの崩れ・安定性の欠如)は解決しません。
そのためPHYSICAL MONSTER ACADEMYでは、
-
呼吸(Breathing)で姿勢と体幹を整える
-
モビリティ(Mobility)で関節の動きを取り戻す
-
モーターコントロール(Motor Control)で正しい動作を再学習する
といった流れで「痛みの再発しにくい身体」をつくっていきます。
5️⃣ ケガの“予防”は、正しく“動く”ことから
ケガを防ぐ最も効果的な方法は、
筋トレでもストレッチでもなく、
**「正しく動ける身体を育てること」**です。
身体の各パーツがバランスよく機能し、
本来の順番で力を伝えられるようになることで、
スポーツ中の負担が減り、パフォーマンスも自然に上がります。
✅ まとめ
-
痛みは「結果」であり、原因は別の場所にある
-
身体は“つながり”の中で動く(運動連鎖)
-
代償動作が続くとケガにつながる
-
回復の第一歩は「正しい動き」を取り戻すこと
💬 保護者の方へ
お子さんが「痛い」と言った時、まずその“背景”を見てあげてください。
痛い場所だけを責めず、身体全体を整えることで、
「痛みの出ない・動ける身体」を取り戻すことができます。
タグ: 身体, 子ども, ストレッチ, 投げる, サッカー, 野球, パフォーマンス, 走る, ケガ, バランス, スポーツ
筋力よりも大事な「動かす順番」 ― 子どもの体を“動作”から整える
タグ: 筋肉, バスケットボール, バレーボール, 子ども, 筋トレ, サッカー, 野球, バスケ, パフォーマンス, スピード, 姿勢, ケガ, 体幹, パワー, 筋力, スポーツ
筋力が弱いのではなく“出力が抑えられている”― パフォーマンス低下の本当の原因
💡 「筋力が足りないから遅い」…本当にそれだけ?
「うちの子、筋力が足りないのかな?」
「もっとトレーニングすれば速く走れるのでは?」
多くの保護者の方がそう感じます。
確かに、筋力を高めることはスポーツの基盤として非常に大切です。
しかし、筋肉をどれだけ強くしても、出力(力の発揮)が抑制されている状態では
本来のパフォーマンスは発揮できません。
⚙️ 出力が抑えられるメカニズム ― “見えないブレーキ”の存在
人の身体は、ケガを防ぐために**神経系による安全装置(抑制機構)**を持っています。
姿勢の崩れ、関節の不安定さ、呼吸の乱れなどがあると、
脳は「このまま力を出すと危険」と判断し、筋出力を自動的に制限します。
たとえば👇
-
骨盤や肩甲骨の位置がずれている
-
呼吸が浅く、腹圧が保てない
-
左右で動きの硬さに差がある
こうした“ズレ”や“偏り”があるだけで、身体はブレーキをかけ、
結果として「力を出しているつもりでも出せない」状態になります。
🧠 「鍛える」+「整える」=本当に強い身体
筋力を上げるトレーニング自体は非常に重要です。
ただし、その効果を最大化するためには、
まず出力を妨げている要因を整えることが欠かせません。
PHYSICAL MONSTER ACADEMYでは、
「鍛える」前に「使える状態に整える」ことを大切にしています。
その流れは次の通りです👇
1️⃣ 呼吸の再教育
腹圧を整え、体幹の安定性を取り戻す。
2️⃣ 可動性と安定性の改善
動くべき関節と支えるべき関節を明確にする。
3️⃣ 運動制御(モーターコントロール)
正しい筋の発火順序で動作を再学習する。
4️⃣ 筋力トレーニングへ発展
抑制が解除された状態で、筋力を効果的に高める。
この順序を踏むことで、筋トレの成果が“本当に使える力”へと変わります。
🚀 出力が整うと、パフォーマンスが劇的に変わる
出力の抑制が解除されると、筋肉同士の連動がスムーズになり、
「力の伝わり方」が格段に良くなります。
🏃♂️ スプリントでは地面を押す力が強くなり、
🏀 ジャンプでは跳び上がりのキレが出て、
⚾ 投球やシュートでは、力を効率的にボールに伝えられるようになります。
つまり、筋力を上げること+出力を引き出すことの両輪が、
本当の意味でのパフォーマンス向上を支えます。
🏫 PHYSICAL MONSTER ACADEMYが大切にしていること
愛知県西尾市のPHYSICAL MONSTER ACADEMYでは、
「筋力を鍛えること」も「出力を整えること」も、どちらも大切にしています。
園児から大学生まで、それぞれの発達段階に合わせて、
呼吸・姿勢・動作・筋力のすべてを評価し、
科学的根拠に基づいたアプローチで指導します。
“強くする”だけでなく、“使える身体をつくる”。
それが、ケガを防ぎ、成長を最大化する近道です。
野球・サッカー・バスケ・バレーなど、
どんな競技の子どもたちにもフィットする“本物のフィジカル教育”を提供しています💪
タグ: 身体, バレー, 力, 子ども, サッカー, 野球, バスケ, シュート, パフォーマンス, 成長, ジャンプ, 姿勢, ケガ, 筋力
トレーニングで痛みが出るのはなぜ? ― 根性論ではなく科学で考える身体づくり
💥 「痛いのは効いている証拠」ではない
「筋肉痛がなければ意味がない」「痛みを乗り越えてこそ成長できる」
そんな言葉を耳にしたことはありませんか?
確かに、トレーニングの翌日に筋肉痛が出ることはあります。
これは、筋繊維が一時的に微細な損傷を受け、
それを修復する過程で強くなっていくという生理的な反応です。
しかし重要なのは――
筋肉痛は「成長に必要条件」ではないということ。
適切なフォームで、筋肉が効率的に使えている場合、
大きな筋肉痛が出なくても十分に効果を得られます。
つまり、「筋肉痛がない=効いていない」ではないのです。
⚠️ 一方で「動作中の痛み」は危険信号
トレーニング中に関節や特定の部位に痛みを感じるとき、
それは身体の使い方にエラーがあるサインです。
「うまく力を伝えられていない」
「どこかの筋肉や関節が代わりに無理をしている」
このような状態を“代償動作”と呼びます。
たとえば:
-
股関節が動かない → 腰が過剰に動く
-
肩甲骨が安定しない → 首や腕が無理する
これを我慢して続けると、
パフォーマンスの低下だけでなく、
慢性的な痛みやケガにもつながります。
🩺 科学的に整える ― 正しいコンディショニングの流れ
痛みを防ぐには、気合いや根性ではなく、
身体の機能を整えるための順序が大切です。
PHYSICAL MONSTER ACADEMYでは、次の4ステップを基本にしています。
1️⃣ 抑制(Inhibition)
働きすぎている筋肉をゆるめる。
2️⃣ 伸張(Lengthen)
硬くなった筋肉を適切な長さに戻す。
3️⃣ 活性(Activation)
使えていない筋肉を呼び覚ます。
4️⃣ 統合(Integration)
正しい動作として全身をつなげる。
この順序で整えていくことで、
動作のバランスが戻り、痛みの原因を根本から取り除くことができます。
💡 「我慢」ではなく「整える努力」を
子どもたちに必要なのは、“耐える力”ではなく、“理解する力”。
-
呼吸を整える努力
-
姿勢を意識する努力
-
自分の身体の反応を感じ取る努力
このような努力が、ケガを防ぎ、
自分の身体を自分でコントロールできる力を育てます。
筋肉痛があってもなくても、それが**「正しく動けている」**証拠なら問題ありません。
🏫 PHYSICAL MONSTER ACADEMYが伝えたいこと
愛知県西尾市のPHYSICAL MONSTER ACADEMYでは、
「痛みを我慢するトレーニング」ではなく、
「痛みを起こさないトレーニング」を大切にしています。
一人ひとりの身体を評価し、
呼吸・可動性・安定性を整えたうえで、
安全にパフォーマンスを高めていく。
トレーニングは“壊す”ものではなく、“育てる”もの。
痛みのない身体で、思いきり動ける未来をつくる。
タグ: コントロール, 安定, 筋肉, 子ども, フォーム, パフォーマンス, トレーニング, 姿勢, ケガ, バランス
🏃♂️ 習い事としてのスポーツトレーニングの価値 ― マルチスポーツが難しい日本でこそ ―
1️⃣ 「競技の前に、体の使い方を学ぶ」
スポーツトレーニングは、競技技術を教える場ではなく、あらゆる競技の基盤となる身体能力を育てる場です。
走る・跳ぶ・投げる・止まる・ひねるなどの「基本動作(Fundamental Movements)」に加え、
持久力・筋力・パワー・柔軟性・バランスといった総合的な体力要素をバランス良く高めます。
これらの能力は、どんなスポーツを選んでも共通して役立ちます。
👉 トレーニング=どんな競技にも通用する「身体能力づくり」です。
2️⃣ 「勝ち負け」よりも「成長」を実感できる
競技スポーツでは結果が基準になりますが、トレーニングは**「過去の自分より上手くできたか」**が評価軸。
この自己比較型の成長体験が、**自己効力感(self-efficacy)**を高め、主体的に行動する力を育てます。
👉 成績ではなく「成長を感じられる」場所。
3️⃣ 「姿勢・集中力・思考力」も育つ“学びの場”
運動は脳を鍛える最良の刺激です。
-
バランスを取る → 体幹と姿勢保持力の向上
-
指示を聞いて動く → 注意・集中力の向上
-
動きを改善して試す → 自己調整力(Self-Regulated Learning)
定期的なトレーニングは、学習面・生活面にも良い影響を与えます。
(参考:Hillman et al., 2008, Neuroscience)
4️⃣ 「ケガをしにくい体」をつくる
成長期の体は、骨の成長スピードに筋肉や腱が追いつかず、アンバランスになりやすい時期です。
正しいフォームと体の使い方を学ぶことで、オスグッド病・腰痛・肩痛などの障害予防につながります。
また、成長期に見られる「クラムジー(clumsy)」=一時的な不器用さも、
多様な動作経験を積むことで自然に改善されていきます。
👉 トレーニングは“未来のケガを防ぎ、動きの質を整える学び”です。
5️⃣ マルチスポーツが難しい日本では「代替」としての価値
欧米では複数のスポーツを経験する「マルチスポーツ文化」が根づいていますが、
日本では部活動やスクール制度の関係から、早期にひとつの競技に固定されがちです。
その結果、動きの多様性が失われ、偏った動作や慢性的な疲労につながることもあります。
👉 スポーツトレーニングは、
複数競技を行う代わりに多様な動作・負荷・環境刺激を体験できる場。
「動きの多様性=発育発達の土台」を確保する代替手段になります。
🔑 まとめ
習い事としてのスポーツトレーニングは、
単なる「運動教室」ではなく、
✅ 競技に縛られずに身体の土台を整える
✅ 成長を自分で実感できる
✅ マルチスポーツの代わりに多様な動きを経験できる
という、現代日本の子どもたちに必要な“第三の選択肢”です。
PHYSICAL MONSTER ACADEMYでは、科学的根拠に基づくプログラムで、子どもたちの身体と心の可能性を育てます💪
タグ: 身体能力, 跳ぶ, 投げる, 成長, 持久力, 走る, トレーニング, 姿勢, ケガ, 体幹, バランス, 柔軟性, パワー, スポーツ