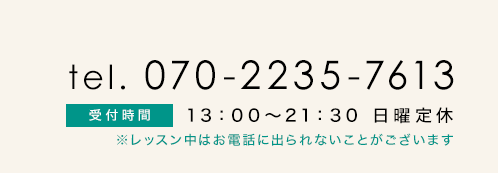成果よりもプロセスを大切にする姿勢 🎯~「うまくいった」より「どうやったか」を育てよう~
1️⃣ 結果だけを見ていませんか?
試合の勝ち負け、タイム、得点、順位…。
スポーツではどうしても**「結果」**が注目されがちです。
しかし、子どもが本当に成長するのは、
「勝った時」ではなく「どう努力したかを考えた時」。
結果は一瞬ですが、
プロセスを考える力は一生の財産になります。
2️⃣ プロセス思考とは「成長の習慣」
プロセスを大切にする姿勢とは、
“なぜ・どうやって・何を変えたか”を意識できることです。
たとえば👇
-
「どうしてこのフォームだとうまくいったんだろう?」
-
「次は何を意識すればもっとよくなるかな?」
-
「うまくいかなかったけど、どんな試し方をした?」
こうした「考える習慣」が身につくと、
練習が単なる作業ではなく、“学び”に変わります。
これはスポーツだけでなく、
勉強・学校生活・人間関係すべてに通じる“成長の型”です。
3️⃣ 結果主義の落とし穴
子どもにとって、「勝てばOK・負ければダメ」という評価軸は、
挑戦への意欲を奪ってしまうことがあります。
特に成長期では、
失敗や試行錯誤の中にこそ“神経系の発達”や“動作学習”が起こるため、
うまくいかない経験こそが成長の材料です。
「今日できなかったことを、どうやってできるようにするか」
その思考こそが“本当の努力”。
結果よりも“そこに至るまでの工夫と挑戦”を認めてあげることで、
子どもは学び続ける力を身につけます。
4️⃣ スポーツ科学が示す「プロセス重視」の意味
学習理論(Self-Regulated Learning)や非線形学習モデルでは、
スキル習得は「一定の成功曲線」ではなく、
上がったり下がったりを繰り返しながら徐々に安定していくと説明されています。
つまり、「できたり、できなかったり」は自然な過程。
それを“失敗”と見るか、“変化の途中”と見るかで成長速度が変わります。
5️⃣ 指導者と保護者ができるサポート 💬
結果よりもプロセスを大切にする文化を育てるためには、
周りの大人の声かけが大きな鍵になります。
❌ 「どうしてできなかったの?」
✅ 「どんな工夫をしたの?」
❌ 「うまくいかなかったね」
✅ 「前より何が変わった?」
たった一言で、子どもの意識は「評価」から「思考」へと変わります。
その積み重ねが、自立的な学びと強いメンタルを育てます。
6️⃣ PHYSICAL MONSTER ACADEMYが大切にしていること
私たちは、**“うまくなる”より“学べるようになる”**ことをゴールにしています。
練習の中で試す → 振り返る → 改善する
このサイクルを大切にすることで、
「指示待ちの選手」ではなく「考えて動ける選手」を育てます。
結果はその先に自然とついてきます。
大事なのは“結果を生み出す力の土台”をつくることです。
✅ まとめ
-
成果よりも「考え方」や「取り組み方」を評価する
-
プロセス思考は失敗を学びに変える力
-
成長とは「結果の積み重ね」ではなく「学びの継続」
-
子どもの挑戦を「結果」ではなく「姿勢」で見守る
疲労と回復 ― 成長期に知っておくべきリカバリーの原則 🧬💤
1️⃣ 「練習すればするほど強くなる」は本当?
スポーツでは「たくさん練習すれば上手くなる」と考えがちです。
でも実際には、成長を決めるのは “疲労と回復のバランス”。
トレーニングによって一時的に疲労が生じ、
身体がそれを回復・適応させる過程で強くなります。
2️⃣ 超回復理論 vs フィットネス–疲労理論
従来よく知られているのが「超回復理論」。
トレーニングで一度下がった能力が、回復によって元より少し高いレベルに戻る――という考えです。
しかし、実際の身体はそんな単純な曲線では表せません。
現代ではより包括的な 「フィットネス–疲労理論(Fitness–Fatigue Model)」 が用いられています。
トレーニングとは、
「プラス(フィットネス効果)」と「マイナス(疲労)」が同時に起こること。
成長とは、疲労が抜けたあとにフィットネス効果だけが残る状態 のことです。
つまり、「やればやるほど伸びる」わけではなく、
“回復を挟んだときにこそ”成長が起こるのです。
3️⃣ 成長期の子どもは“疲れにくく・回復しやすい”
最新の研究では、子どもは大人に比べて👇
-
有酸素的エネルギー供給が優位
-
乳酸の蓄積が少ない
-
神経系の回復が速い
といった特徴があり、一時的な疲労からの回復はむしろ速いことが分かっています(Ratel & Duché, 2012)。
しかし注意が必要なのは👇
-
筋・腱・骨などの組織強度はまだ弱い
-
疲労を感じにくく、無理をしやすい
-
蓄積疲労が「成長痛」や「オーバーユース障害」につながる
つまり、「回復が速い=安全」ではなく、
“感じにくい疲労”をどう管理するかが重要なのです。
4️⃣ 科学的リカバリーの3原則
💤 ① 睡眠(Sleep)
最も効果的で、かつ見落とされがちな回復手段。
🍽️ ② 栄養(Nutrition)
トレーニング後30分以内の栄養補給が理想。
糖質とタンパク質を一緒に摂ると、筋回復とグリコーゲン補充が進みます。
例)牛乳+おにぎり、プロテイン+果物、鶏むね肉+ごはん
🧘♂️ ③ アクティブリカバリー(Active Recovery)
完全休養よりも、軽い運動やストレッチで血流を促す“積極的休養”が効果的。
例)軽いジョギング、フォームローラー、呼吸ドリルなど。
5️⃣ 「疲労の質」を見極める
すべての疲労が同じではありません👇
-
身体的疲労:筋肉や関節の疲れ
-
神経的疲労:反応や集中力の低下
-
心理的疲労:ストレスやモチベーションの低下
どのタイプの疲労が溜まっているかを観察し、
リカバリー方法を使い分けることが大切です。
6️⃣ トレーニングとリカバリーは表裏一体
PHYSICAL MONSTER ACADEMYでは、
「トレーニング=身体に刺激を与える時間」
「リカバリー=その刺激を成長に変える時間」
という考え方でプログラムを設計しています。
✅ まとめ
-
成長は「トレーニング中」ではなく「回復中」に起こる
-
超回復理論だけでなく「フィットネス–疲労理論」で考えるのが現実的
-
子どもは疲労からの回復が速いが、組織損傷リスクは高い
-
睡眠・栄養・アクティブリカバリーの3本柱で安全に成長を支える
ダーウィン進化論に学ぶ「変化に適応する力」 🌍💪~強さよりも、しなやかさが未来を切り開く~
1️⃣ 「強い者が生き残るわけではない」
生物学者チャールズ・ダーウィンの言葉として有名なのが、
「最も強い者が生き残るのではなく、変化に適応できる者が生き残る」。
これは自然界の話ですが、
実はスポーツやトレーニングにもそのまま当てはまる考え方です。
子どもの成長期の身体や環境は常に変化しています。
筋力、身長、神経系、仲間、ルール、ポジション…。
その中で成果を出し続ける選手に共通しているのは、
「変化を恐れず、適応できる力」を持っていることです。
2️⃣ スポーツにおける“適応力”とは?
適応とは、環境の変化に合わせて動き・思考・戦略を柔軟に変えられる力のことです。
スポーツでは、同じフォームやプレーを完璧に再現するよりも、
状況に合わせて微調整できる方がパフォーマンスは安定します。
🏀 コートの滑りやすさ
⚾ 相手ピッチャーの球質
⚽ 風向きやグラウンドの状態
こうした環境変化の中で、
“どう動くかを自分で考えて修正できる力”=適応力が問われます。
3️⃣ トレーニングでも「変化」を恐れない
従来のトレーニングでは、
「同じフォームを正確に繰り返す」ことが良しとされてきました。
しかし最新のスポーツ科学(エコロジカル・ダイナミクス理論)では、
「常に同じ」よりも「少しずつ違う条件で動く」ことが、より高い学習効果を生む
と考えられています。
たとえば👇
-
足場を変える(マット・芝・バランスパッド)
-
道具を変える(重さ・形・反発)
-
視覚情報を変える(目を閉じる・動く的を狙う)
このような“環境の変化(制約)”が、
子ども自身の身体感覚・判断力・バランス感覚を研ぎ澄まし、
どんな状況でも崩れない「安定した動き」を育てます。
4️⃣ 「安定×変化」の両立が成長の鍵
変化に適応するためには、
ただ“ブレる”だけでなく、**安定した軸(アトラクター)**が必要です。
安定性(アトラクター)と揺らぎ(フラクチュエーション)は、
ダーウィン進化論の「適応」そのもの。
🧩 安定性=基本となる動きの構造(身体の使い方)
🌊 揺らぎ=環境や課題に合わせて動きを変える柔軟性
この両方を持つことで、選手は環境変化に強くなります。
「常に変化する」ことが、最も“安定した成長”を生むのです。
5️⃣ 保護者が育てられる“適応力” 💬
子どもの「変化への適応力」は、家庭でも育てられます。
❌ 「前はできたのに、なんでできないの?」
✅ 「今日はどんな感じだった? どう変えてみようか?」
と声をかけるだけで、
「変化を恐れず、工夫して対応する力」が養われます。
失敗やうまくいかない経験は、進化の“材料”。
変化を受け入れ、試行錯誤を繰り返すことこそが、
子どもを本当に強くしていきます💡
✅ まとめ
-
ダーウィンの進化論は「変化に適応できる者が生き残る」と教えている
-
スポーツでも“完璧な形”より“柔軟な対応力”が重要
-
環境変化に慣れるトレーニングが、安定したパフォーマンスを生む
-
保護者の声かけ一つで、「変化を恐れず考える力」が育つ
学習姿勢が子どもの成長を決める 💪🧠~“できる”より“どう学ぶか”が大切~
1️⃣ 結果よりも「姿勢」が子どもを伸ばす
スポーツや勉強で成長する子に共通しているのは、
「上手い」「才能がある」ことではなく、学ぶ姿勢が前向きなこと」。
どんなに良いトレーニング環境や指導者がいても、
本人に「学ぼう」という姿勢がなければ成果は続きません。
反対に、ミスを恐れず挑戦し、失敗から学ぼうとする子は、
どんな環境でもぐんぐん伸びていきます🌱
2️⃣ 学習姿勢とは?
学習姿勢とは、**「課題に向き合うときの心の構え」**のこと。
具体的には次のような力を指します👇
-
💡 目的意識:「なぜこれをやるのか?」を理解している
-
🔁 粘り強さ:うまくいかなくてもすぐに諦めない
-
🔍 ふり返り力:「どうすればもっと良くなる?」を考えられる
この3つが揃うと、どんなトレーニングでも「成長のチャンス」に変わります。
3️⃣ “できるかどうか”より“どう取り組むか”
同じ練習をしても、結果が大きく変わることがあります。
違いを生むのは「やり方」ではなく、「取り組み方」。
例えばスクワットをする時👇
-
指示通りにただ回数をこなす子
-
「どこを意識すると安定するか」「次はどう変えてみよう」と考える子
後者の方が、フォームも感覚も速く成長します。
それが、自己調整学習(SRL) の第一歩です。
4️⃣ 成長を支える“3つの学習姿勢”
1️⃣ 目的をもって行う(Plan)
→ 「今日は姿勢を安定させよう」など、自分で目標を立てる。
2️⃣ 考えながら行う(Do)
→ 動きの中で意識を変えたり、工夫したりする。
3️⃣ ふり返って学ぶ(Reflect)
→ 「どこが良かった?」「次はどうする?」と省察する。
このサイクルを繰り返すことで、
“教わる子”から“自分で伸びる子”へと変わっていきます。
5️⃣ 指導者や保護者にできること 💬
学習姿勢は「声かけ」で大きく変わります。
❌ 「なんでできないの?」
✅ 「どうしたらできそう?」
❌ 「早く終わらせて」
✅ 「どこを意識してやってみる?」
このように、答えを教えるのではなく“考えるきっかけ”を与える ことで、
子どもの学習姿勢は自然に育ちます。
6️⃣ 学ぶ姿勢が“人生の基礎体力”になる
スポーツのトレーニングで身につく「学習姿勢」は、
勉強・人間関係・将来の挑戦にもつながります。
「うまくいかなかったけど、次はこうしてみよう」
この一言が言える子は、
どんな環境でも成長し続ける“強い学習者”になります💫
✅ まとめ
-
成長を決めるのは「学ぶ姿勢」
-
SRL(自己調整学習)は“考えて動く”力を育てる
-
指導者・保護者は「教える」より「気づかせる」サポートを
-
どんな練習も“考え方次第”で成長のきっかけに変わる
自己調整学習(SRL)と制約主導アプローチ(CLA)で子どもの主体性を育てる 🧠✨
1️⃣ 「やらされる練習」では伸びにくい時代へ
スポーツの現場では、「言われた通りにやる」だけでは子どもの力は伸びません。
必要なのは、「自分で考え、修正し、成長できる力」。
その力を育てるのが、
👉 自己調整学習(Self-Regulated Learning:SRL) と
👉 制約主導アプローチ(Constraint-Led Approach:CLA) です。
2️⃣ 自己調整学習(SRL)とは?
SRLとは、
「自分で目標を立て、実行し、振り返り、次の行動に生かす力」
のことです。
つまり、コーチに言われたからやるのではなく、
「どうすればもっと良くなるか」を自分で考えられる選手を育てる考え方です。
SRLの3ステップ
1️⃣ 目標を立てる(計画)
→ 「今日は姿勢を安定させよう」
2️⃣ やってみる(実行)
→ 自分の身体感覚を意識しながらトライする
3️⃣ 振り返る(評価)
→ 「どうしたらもっとやりやすくなるか」を考える
この繰り返しで、自分で考えて成長できる選手になります。
3️⃣ 制約主導アプローチ(CLA)とは?
CLAは、**「教えすぎず、環境で導く」**という考え方です。
指導者が「こう動いて」と正解を教える代わりに、
「環境」「道具」「課題(制約)」を工夫して、
子どもが 動きながら自分で“うまくいく方法”を見つける ように促します。
4️⃣ 現場での実践例
たとえば、スクワットの姿勢が安定せず、膝が前に出てしまう子がいたとします。
❌ 従来型の指導
「もっと背筋を伸ばして!」
「膝を前に出さないで!」
➡ 指示ばかりになり、子どもは“外からの言葉”に頼るようになります。
✅ CLA+SRL型の指導
「じゃあ、ボックス(椅子や台)を使ってやってみよう」
(※しゃがむ深さを制限する“制約”を設ける)
➡ すると、自然と膝が前に出にくくなり、重心を後ろに保つ感覚をつかめる ようになります。
子どもは「どの深さなら安定して力を出せるか」「どう動くとスムーズに立てるか」を、体感的に学んでいく のです。
このとき、指導者は「そのフォームが安定してるね」「どうするとやりやすかった?」と問いかけ、
自分で気づき・考えるプロセス(SRL) を促します。
CLAが「学びを引き出す環境」をつくり、
SRLが「自分で調整して成長する力」を育てる――
この2つが組み合わさることで、子どもは“自分でうまくなる”力を身につけていきます。
5️⃣ “教える”から“気づかせる”へ
子どもが本当に成長するのは、
「できるようにさせられたとき」ではなく、
「できた理由に自分で気づいたとき」です。
CLAとSRLの考え方は、
「教える指導」から「気づかせる指導」へと変えていくものです。
6️⃣ 保護者ができるサポート 💬
家庭でもSRLの力を育てることができます。
🗣️ 練習やトレーニングのあとに、こんな声かけをしてみてください👇
-
「今日の練習でうまくできたことはどこ?」
-
「うまくいかなかったとき、どうしたら良くなると思う?」
-
「次の練習では何を意識してみたい?」
こうした対話が、お子さんの“考える習慣”を育てます。
✅ まとめ
-
SRL(自己調整学習) は「自分で考え、修正し、再挑戦する力」
-
CLA(制約主導アプローチ) は「その力を引き出す環境設計」
-
教えすぎず、環境で気づかせる
-
指導者・保護者の“問い”が、子どもの主体性を動かすカギ
コルブの経験学習理論とスポーツ現場 🎯
~「やって終わり」にしない学び方のデザイン~
1. 経験から学ぶ ― Kolbの4つのサイクル
アメリカの教育学者 デイヴィッド・コルブ(David Kolb) は、
「人は経験から学ぶ」という考えを体系化しました。
その学びのプロセスは4つの段階から成り立っています👇
1️⃣ 具体的経験(Concrete Experience)
→ 実際にやってみる・体験する。
(例:新しい動きを練習する、試合に出る、ミスを経験する)
2️⃣ 省察的観察(Reflective Observation)
→ その経験を振り返る。
(うまくいかなかった理由、どう感じたかを考える)
3️⃣ 抽象的概念化(Abstract Conceptualization)
→ 振り返りから理論や考え方を導く。
(なぜそうなったのか?何を変えればいいか?)
4️⃣ 能動的実験(Active Experimentation)
→ 新しい考えをもとに行動を変えて試す。
(フォームを修正する、新しい戦術を試す)
この4つのサイクルを繰り返すことで、学びが深まり、「できる」から「理解して使える」へ 変わっていきます。
2. スポーツ現場では「経験で終わる」ことが多い
スポーツの練習や試合は、まさに「具体的経験」の宝庫です。
しかし、多くの場合、練習や試合が 「やって終わり」 になってしまっています。
-
ミスしても次のプレーにすぐ移る
-
「もう一回やれ!」で終わる
-
なぜうまくいかなかったかを考える時間がない
これでは 経験が“消費”で終わってしまい、“学習”にはなりません。
3. 経験を“学び”に変える仕組みが必要
スポーツ現場で重要なのは、経験を振り返る時間と対話です。
たとえば、
-
「なぜ今のプレーはうまくいかなかったと思う?」
-
「次に同じ場面が来たらどうする?」
といった問いかけをすることで、子どもたちは自分の中に「学びの回路」を作り始めます。
これがまさに、省察的観察 → 抽象的概念化 のステップです。
4. S&C(ストレングス&コンディショニング)にも当てはまる
トレーニングも同じです。
ただ動くだけでは「経験」で終わりますが、
-
なぜこの種目をやるのか
-
どこを意識すべきなのか
-
終わったあとにどう感じたか
こうした問いを入れることで、トレーニングが“学び”に変わるのです。
特に子どものうちは、「考えるトレーニング」を通して
自己理解・身体感覚・判断力 が育ちます。
5. 保護者・指導者ができること 💡
-
練習や試合後、「どうだった?」と聞く時間をつくる
-
失敗を責めず、「次にどうする?」の視点で対話する
-
結果だけでなく「考えた過程」を認める
この小さな積み重ねが、子どもの「学習サイクル」を回すサポートになります。
✅ まとめ
-
コルブの経験学習理論は「体験→振り返り→理解→実践」の4段階
-
スポーツは経験が多いが、振り返りが少ないと“学び”にならない
-
S&Cでも、動くだけでなく「なぜ・どう感じた」を意識することで効果が高まる
-
経験を“学び”に変える仕組みが、選手の成長を支える
WHYから始めるトレーニング設計 💡
~“何をするか”よりも、“なぜやるか”を考える~
1. トレーニングの出発点は「なぜ」から
トレーニングを考えるとき、最初に浮かびやすいのは「何をするか(WHAT)」です。
「スクワットをやろう」「走り込みをしよう」「体幹を鍛えよう」など、メニューそのものに意識が向きがちです。
しかし、本当に大切なのは 「なぜそれをやるのか?」(WHY) です。
目的が明確でなければ、どれだけ良いメニューを積み重ねても、その効果は最大化されません。
2. WHY → HOW → WHAT の順で考える
トレーニングを効果的に設計するためには、以下の順番が基本です。
1️⃣ WHY(目的):
何のために行うのか?
→ 例:「ジャンプ力を上げたい」「ケガを予防したい」「スプリントの加速を高めたい」
2️⃣ HOW(方法):
どんな原理で改善できるのか?
→ 例:「下肢の力発揮速度を高める」「体幹の安定性を上げる」「動作の連動性を整える」
3️⃣ WHAT(内容):
具体的に何をするのか?
→ 例:「スクワット」「プライオメトリクス」「メディシンボールスロー」
この順番を逆にしてしまうと、「なんとなくやっているトレーニング」になってしまいます。
3. 現場では“WHAT”から始まりがち
多くの現場では、限られた時間の中で「とりあえず動かす」「とりあえずメニューを組む」ことが先になりがちです。
しかし、それでは“目的と方法が一致しないトレーニング”になる危険があります。
たとえば、「ケガを減らしたい」と言いながら、疲労をためるような負荷設定をしてしまうケース。
このように WHYを無視したトレーニングは、良い意図があっても逆効果になることがあります。
4. PHYSICAL MONSTER ACADEMYの考え方
私たちが大切にしているのは、「プログラムはメニューの集まりではない」 という考え方です。
それぞれの種目には明確な“意図”があり、すべてがつながっています。
-
WHY:お子さんの課題(姿勢・動き・筋力など)を明確にする
-
HOW:その課題を改善するための原理を選ぶ
-
WHAT:最適なトレーニング手段を選択する
この順序で設計することで、安全で効果的、かつ継続的な成長を支えられるのです。
5. 保護者の方へメッセージ 💬
「トレーニング=筋トレ」ではありません。
筋トレも走りもストレッチも、すべては目的を達成するための“手段”です。
お子さん一人ひとりの「なぜ」に合わせて設計することが、成長を最短で引き出す近道です。
✅ まとめ
-
トレーニングは WHY(目的)から始める のが原則
-
HOW(方法)とWHAT(内容)は、その目的を達成するための手段
-
「なんとなくやる」から「意図を持ってやる」へ
-
目的に沿った設計が、最短で最大の成果を生み出す
特異性の原則 ― 似た動きではなく“目的に合った刺激”を選ぶ 🎯
1. 特異性の原則とは?
トレーニングの世界には「特異性の原則」という考え方があります。
これは 与えたストレスの種類に応じて、その適応も特異的に起こる というものです。
つまり「どんな刺激を身体に与えるか」が、そのまま「どんな成長をするか」を決めるのです。
2. よくある誤解
「特異性」と聞くと、
👉 「競技の動きにそっくりな練習をすればいい」
と思われがちです。
たしかに、始めたばかりの子どもにとっては競技そのものの動作が新しい刺激となり、十分に成長につながります。
しかし経験を積んだ選手の場合、競技動作はすでに身体が慣れてしまっているため、それ以上の成長刺激にはなりにくいのです。
3. 本当の特異性は「動き」ではなく「刺激の質」
特異性の原則が意味するのは、
「見た目の動きが競技に似ているかどうか」ではなく、
「その動作でどんな刺激を身体に与えているか」です。
-
速さを伸ばしたいなら「短時間で大きな力を出す刺激」
-
パワーを伸ばしたいなら「爆発的な力発揮の刺激」
-
持久力を伸ばしたいなら「長時間続ける負荷」
👉 目的と刺激が合っていなければ、能力は伸びません。
4. 子どもの成長にどう関わる?
-
初心者の段階
競技そのものが新しい体験であり、それだけで大きな刺激となります。
走る、跳ぶ、投げるといった動き自体が新しい負荷になるため、
競技をするだけでフィジカル(筋力・瞬発力・持久力・柔軟性など)も一緒に伸びていきます。 -
経験を積んだ段階
競技動作に身体が慣れてしまい、もはや新しい刺激にはなりません。
➡ この段階では「競技だけ」ではフィジカルの成長は頭打ちになり、
競技以外での補強トレーニング(ウェイト・プライオメトリクス・モビリティなど) が必要になります。
5. 保護者の方へメッセージ 💡
「競技練習だけをたくさんやれば強くなる」と思われがちですが、実際にはそうではありません。
-
競技練習は“スキル”を磨くもの
-
トレーニングは“能力”を伸ばすもの
能力を伸ばしてこそ、スキルがさらに生きるのです。
だからこそ、私たちは「特異性の原則」に基づいて、目的に合った刺激を組み込んだプログラムを提供しています。
✅ まとめ
-
特異性の原則=「動きの類似」ではなく「刺激の質」によって決まる
-
初心者は競技動作そのものが刺激になり、フィジカルも伸びる
-
経験者は競技だけでは新しい刺激が得られず、成長は頭打ちになる
-
S&Cプログラムは、その“不足する刺激”を計画的に補う役割を果たしている
トレーニングに「原理原則」が必要な理由 🏋️♂️✨
はじめに
SNSや雑誌には「最新の筋トレ法💡」「魔法のストレッチ✨」といった情報があふれています。
でも本当に子どもの成長やスポーツパフォーマンスを伸ばすためには、流行のやり方を追いかけるのではなく、 普遍的なルール=原理原則(Principles) を大切にすることが必要です。
ダイエットやボディメイクとスポーツパフォーマンスは違う ⚡
「痩せるための運動」と「速く走る・高く跳ぶ・ケガを防ぐための運動」は全くの別物です。
スポーツパフォーマンス向上のトレーニングは、筋肉を大きくすることではなく 実戦で動ける身体を作ること がゴールです。
スクワットは大事、でも… 🤔
スクワットが重要なのは誰もが知っています。
しかし大切なのは「何回?どのくらいの重さ?どんなテンポ?休憩は?」などの条件をどう設計するか。
プロのS&Cコーチはこうした要素を組み合わせ、同じスクワットでも効果を最大化します。
メニューではなく「プログラム」🍽️
一般的な「メニュー」とは違い、S&Cが作るのは「プログラム」。
それはまるで コース料理 のように、順序や役割を考えて組み立てられています。
実際のプログラムの流れ 🌱➡🔥➡🛌
🌱 リセット(Reset)
呼吸や軽い動きで心と身体をニュートラルに。集中力を高める準備。
🌬 ブリージング(Breathing)
正しい呼吸を学び、体幹の安定やリラックス、疲労回復へ。
🤸 モビリティ(Mobility)
関節の柔軟性を広げ、ケガを防ぎながらしなやかに動ける体を作る。
🎯 モーターコントロール(Motor Control)
姿勢やフォームを意識し、思い通りに体を動かす力を育てる。
🚀 ムーブメントプレパレーション(Movement Preparation)
ウォーミングアップで神経や筋肉を刺激し、動きやすい体へ。
🏃 ムーブメントスキル(Movement Skills)
走る・切り返す・加速するなど、スポーツの基盤となる動きを習得。
🔥 プライオメトリクス(Plyometrics)
ジャンプや反発動作で瞬発力を鍛え、爆発的なパワーを育てる。
🏐 メディシンボール(Medicine Balls)
全身を使った投げ動作で体幹と連動性を強化。「安全に全力を出す」感覚を学ぶ。
🏋️ ストレングスパワー(Strength-Power)
-
トラディショナル:スクワットやベンチプレスなど基礎筋力を積み上げる。
-
トランスファー:フィジカルを実際のスポーツパフォーマンスに転移させることを重視したトレーニング
⏱ ESD(Energy System Development)
持久力やスタミナを高め、最後まで走り切れる身体を育てる。
🛌 リジェネレーション(Regeneration)
ストレッチや整理運動で回復を促し、次の成長につなげる。
成長を支える「4つの原理原則」📘
-
過負荷の原則 💪 … 今より少し強い刺激を与える。
-
漸進性の原則 📈 … 負荷は少しずつ高める。
-
特異性の原則 🎯 … 効果は「与えたストレスの種類」に特異的に現れる。
-
可逆性の原則 🔄 … 継続しなければ効果は失われる。
まとめ ✨
✅ メソッドは無数にあるが、原理原則は普遍的。
✅ 子どもの成長を考えるなら「メニュー」ではなく「プログラム」が必要。
✅ 流れに沿ったトレーニングこそ、安全で効果的に子どもを伸ばす。
私たちは、この原理原則に基づいたプログラムを提供し、安心して成長できる環境を整えています💪🔥
💥 頑張りすぎが逆効果? 🏃♂️⚽ スポーツが上手な子ほど気をつけたいケガのリスク 🤕
「上達するには、とにかく同じ練習をたくさんやることが大事」
そう思われがちですが、実はこれはケガのリスクを高める原因になることがあります。
子どもたちが安全に、かつ効率的にスキルを身につけるためには、オーバーユース(使いすぎ)を防ぎながら多様な練習を行うことが重要です。
🔹 オーバーユースとは?
オーバーユース(Overuse)とは、同じ動作を繰り返しすぎて、関節や筋肉に過度な負担がかかり、ケガや障害につながることを指します。
-
野球:投げすぎによる肩や肘の障害
-
サッカー:蹴りすぎや走りすぎによる膝や股関節の痛み
-
陸上:走り込みすぎによるシンスプリントや疲労骨折
これらは「使いすぎ」が原因で起こる典型例です。
🔹 スキル獲得と反復練習の関係
スキルは反復によって身につきます。
しかし「同じ動きを同じ形で繰り返す」ことは、実は人間の神経系にはそぐわない練習方法です。
👉 運動学習の理論(Bernstein, Ecological Approach)によると、
-
人間は毎回少しずつ異なる動きでタスクを解決している
-
多様な状況で動きを試すことで「適応できるスキル」が育つ
つまり、「反復のない反復」=同じ結果を得るために多様な動きを試す ことが、スキル獲得を加速させます。
🔹 出力の高い子ほど注意が必要
特に気をつけたいのが、**運動能力が高くて目立つ子(エースやレギュラー選手)**です。
1️⃣ 出力が大きい=関節や筋腱への負荷も大きい
速い球を投げられる子や高く跳べる子は、同じ動作でも他の子より骨・筋・関節に強いストレスをかけています。
2️⃣ 試合や練習で“頼られすぎる”
「チームのエースだから」「レギュラーだから」といった理由で、無意識に練習量や試合出場時間が増え、休む機会を失いがちです。
3️⃣ 成長のスピードと耐久性のギャップ
成長期ではパフォーマンスだけ先に伸び、骨や腱など組織の耐久性が追いつかないため、ケガのリスクが高まります。
👉 つまり「できる子ほどケガをしやすい」という落とし穴があるのです。
🔹 ケガを防ぐ賢い練習法
1️⃣ 負荷と休養のバランスをとる
練習量は「できるから増やす」ではなく、「体が回復できる範囲」で調整する。
2️⃣ 多様な動きを取り入れる
投げる動作なら角度や距離を変える、ジャンプなら方向やリズムを変えるなど、同じ部位に負担を集中させない。
3️⃣ 体づくりとスキル練習を組み合わせる
臀筋・体幹・肩甲帯の安定性など「基礎体力の土台」がスキルを支えます。
4️⃣ 休養の質を高める
👪 保護者の方へ
「うちの子はチームで一番動けるから安心!」
そう思っていても、実は出力の高い子ほどケガのリスクは高いのです。
👉 保護者が「もっとやらせる役」ではなく、時にブレーキをかける役割を担うことが、子どもの将来を守ります。
✅ まとめ
-
オーバーユース=同じ動作の繰り返しで起こる障害
-
スキル獲得には「反復のない反復」が必要
-
出力の高い子ほどオーバーユースに注意
-
ケガを防ぐには「多様性+回復+基礎体力」
👉 PHYSICAL MONSTER ACADEMY では、最新のトレーニング科学と子どもの発達特性を踏まえ、ケガを防ぎながらスキルを伸ばす環境を整えています。