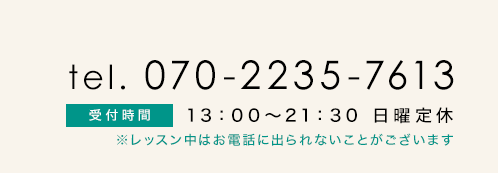🛌 Regeneration ― 回復
トレーニングは「やればやるほど強くなる」と思われがちですが、実際には 回復(Regeneration) の質がパフォーマンスを左右します。
体を追い込むだけでなく、しっかりと休養をとることで成長が最大化されるのです。
🔄 超回復とフィットネス‐疲労理論
従来よく知られている「超回復(Supercompensation)」では、トレーニング後に一度下がったパフォーマンスが、休養を経て以前より高いレベルに戻るとされています。
しかし、実際の競技現場ではそれだけでは説明できません。
現在では フィットネス‐疲労理論(Fitness-Fatigue Theory) が広く用いられています。
-
トレーニングは「プラスの適応(フィットネス)」と「マイナスの疲労」を同時に生む
-
休養をとることで疲労が抜け、フィットネス効果だけが残る
-
これを繰り返すことでパフォーマンスが右肩上がりになる
👉 大切なのは「練習と休養のバランス」をコントロールすることです。
⏰ 睡眠 ― 最強のリカバリー手段
子どもの回復で最も重要なのは 睡眠 です。
成長ホルモンの分泌、神経系の修復、記憶の定着など、すべて睡眠中に行われます。
👉 夜更かしや睡眠不足は、集中力の低下・ケガのリスク増加・成長の停滞に直結します。
🍽 栄養と水分
回復の土台を支えるのは食事と水分補給です。
-
トレーニング直後は糖質+たんぱく質で筋修復をサポート
-
日常的に野菜・果物からビタミン・ミネラルを摂取
-
水分は「のどが渇いた時」では遅く、こまめな補給が大切
🧘♂️ アクティブリカバリー
完全な休養日だけでなく、軽い運動で血流を促す アクティブリカバリー も有効です。
-
軽いジョグやサイクリング
-
ストレッチやヨガ
-
呼吸法によるリラックス
これにより疲労物質の代謝が進み、回復が早まります。
👪 保護者の方へ
「頑張らせる」だけでなく「休ませる」ことも成長の一部です。
回復を適切にとることで、子どもたちは ケガを減らし、成長曲線を加速させる ことができます。
✅ まとめ
-
回復(Regeneration)はトレーニング効果を最大化する鍵
-
超回復よりも「フィットネス‐疲労理論」で理解することが重要
-
睡眠・栄養・水分・アクティブリカバリーが子どもの成長を支える
👉 PHYSICAL MONSTER ACADEMY では、トレーニングだけでなく「回復力」を育むことも重視し、子どもたちの成長を全方位からサポートしています。
筋肉の震えについて
こんにちは!💪
今日は多くの方が一度は経験したことがある「筋肉のプルプル震え」について解説します。トレーニング中や細かい作業をしている時に手や足が震えるのはなぜなのか?その背景には筋肉や神経の精密な仕組みが隠されています。
🔬 シグナル依存性ノイズとは?
脳から筋肉に「動け!」という指令が送られる時、その信号の量が多いほど ノイズ(誤差) が増えます。
これにより、動きの精度や反応速度が悪化し、プルプルと震えが出やすくなります。
つまり、大きな力を出そうとすればするほど、誤差や震えも大きくなる のです。
😵 疲労による影響
トレーニングや長時間作業をすると筋肉や神経は疲れてきます。その結果…
-
筋肉を動かす神経の発火が安定しなくなる
-
拮抗筋(反対の動きをする筋肉)とのバランスが崩れる
-
感覚フィードバックが遅れ、補正動作が増える
👉 これらが積み重なり、ガクガクとした震え へとつながります。
👀 細かい作業で震える理由
なぜ針の穴に糸を通すような細かい作業では震えが強く出るのでしょうか?
-
生理的な振戦(自然な8〜12Hzの揺れ)
-
緊張や不安などの交感神経の影響
-
シグナル依存ノイズ
-
視覚フィードバックの遅延(100〜200ms程度)
特に視覚の遅れによって 「修正 → 過修正 → 逆修正」 が繰り返され、小さな震えが増幅されやすくなります。
⚖️ 出力戦略(震えを抑える方法)
筋肉の震えは完全にはなくせませんが、コントロールすることは可能です。
-
予備収縮(preload)を入れる
👉 発火しにくい筋をあらかじめ軽く働かせておくことで、動作中に急な力みや強すぎる共収縮を防ぐ。
👉 「眠っている筋を呼び覚ます点火作業」と考えるとわかりやすいです。 -
最小安定力を探す
👉 必要以上に強く力まず、安定できる最小限の力で構える。 -
テンポを付けた運動
👉 リズムを持たせることで、フィードバックの遅れによるガタつきを減らす。 -
視覚の使い方を工夫
👉 視野を広くとり、対象を凝視しすぎないようにする。
🏋️♂️ まとめ
筋肉のプルプル震えは「弱いから」ではありません。
実は、脳・神経・筋肉がフル稼働しているサイン でもあります。
-
信号ノイズの影響
-
疲労による神経活動の乱れ
-
視覚フィードバックの遅延
-
そして「眠っている筋を点火する予備収縮」の有無
これらが組み合わさって震えが起こります。
🏃♂️ ESD(Energy System Development)― 持久力とエネルギー供給を鍛える
「体力=長く走れること」と思われがちですが、スポーツで本当に必要なのはそれだけではありません。
大切なのは 必要な瞬間に、必要なだけのエネルギーを生み出す力 です。
🔋 エネルギーシステムの3つの働き
人間の体は運動の強度や時間に応じて、次の3つのエネルギーシステムを切り替えながら動きます。
-
ATP-PCr系(瞬発系)
数秒のダッシュやジャンプなど「一瞬の爆発力」を支える。 -
解糖系(中間持久系)
30秒〜2分程度の高強度動作を繰り返す場面で活躍。 -
有酸素系(持久系)
長時間の運動や、全体を動き切る持続力・回復力を支える。
👉 スポーツではこれらが単独ではなく、組み合わせて機能する のが特徴です。
⚡ 子どものESDで大切なこと
成長期の子どもに必要なのは「ただ長く走れる持久力」ではなく、
爆発的な動きと、その回復を繰り返せる力 です。
-
サッカー → ダッシュとリカバリーを何度も繰り返す
-
バスケットボール → 速攻とディフェンスの連続
-
野球 → 投球や打撃を試合を通じて繰り返す
-
柔道・ラグビー → 接触と動きの持続
👉 つまり「瞬発力+持久力のバランス」を育てることがESDの本質です。
🏋️♂️ アカデミーでの実施方法
PHYSICAL MONSTER ACADEMYでは、マラソンのような長距離走は取り入れていません。
限られたスペースでも実施できる 短時間・多様な動き を通してエネルギーシステムを鍛えています。
-
短いダッシュの繰り返し → ATP-PCr系を刺激
-
方向転換やジャンプ動作 → 解糖系を活性化
-
高強度インターバル(HIIT・タバタ式など) → 瞬発系と解糖系を刺激しつつ、有酸素系の土台も効率的に強化
👉 HIITやタバタは「有酸素系専用」ではなく、全エネルギーシステムを同時に刺激できる効率的な方法です。
⚽ スポーツへの応用
-
サッカー:90分戦い抜きつつ、最後までダッシュできる力
-
バスケ・バレー:連続ジャンプや速攻を繰り返す力
-
野球:投球や打撃の瞬発力を最後まで維持する力
-
柔道・ラグビー:接触プレーに耐え抜く力
👪 保護者の方へ
「体力をつける=長距離を走る」と考える方も多いですが、現代のスポーツで必要なのは 瞬発力と回復力を繰り返せる力 です。
短時間で効率よく鍛えるトレーニング(HIIT・タバタなど)を取り入れることで、成長期の子どもでも安全に「走れる・動ける・最後までやり切れる」体を育てられます。
✅ まとめ
-
ESD=エネルギー供給システムを鍛えるトレーニング
-
子どもに必要なのは「長距離走の持久力」ではなく「瞬発力+回復力」
-
HIITやタバタは全エネルギーシステムを同時に刺激できる効率的な方法
-
サッカー・バスケ・野球・柔道など、全スポーツに直結
👉 PHYSICAL MONSTER ACADEMYでは、科学的に設計されたESDを通じて、子どもたちが最後まで全力でプレーできる体をサポートしています。
💪 Strength-Power ― 筋力とパワーの基盤づくり
スポーツで必要な「速さ」「強さ」「高く跳ぶ力」はすべて 筋力(Strength)とパワー(Power) を土台としています。
筋力がなければパワーは発揮できず、パワーがなければ競技動作に直結しません。
この2つをバランスよく高めることが、成長期の子どもにとって重要です。
🔬 筋力とパワーの違い
-
筋力(Strength):最大限に力を発揮する能力(例:重いものを持ち上げる)
-
パワー(Power):力 × 速度(F × V)で表される「短時間に大きな力を出す能力」
👉 筋力=エンジンの大きさ
👉 パワー=エンジンを一気に加速させる力
⚡ 力―速度関係(F-V Curve)
筋肉は「重いものをゆっくり動かす」か「軽いものを速く動かす」か、どちらかに偏ります。
-
大きな力(F)=遅い動き(例:重量スクワット)
-
大きな速度(V)=小さい力(例:スプリントやジャンプ)
👉 理想は 力と速度の両方を高め、カーブ全体を押し上げること。
これがパフォーマンスの最大化につながります。
⚡ RFD(力の立ち上がり率)
スポーツ動作は0.1〜0.2秒で勝負が決まります。
そのため「最大の力」よりも どれだけ素早く力を立ち上げられるか が重要です。
-
スプリントの接地:0.1秒以下
-
跳躍や切り返し:0.2秒前後
👉 RFDが高いほど、爆発的で素早い動きが可能になります。
🏋️ トレーニングの具体例
-
高重量・低速(ウェイトトレーニングなど) → 最大筋力(F)を高める
-
軽負荷・高速(ジャンプやスプリントなど) → 速度(V)やRFDを高める
-
中間負荷・爆発的動作(オリンピックリフティング、メディシンボールなど) → 力と速度を同時に伸ばす
⚽ スポーツ応用
-
野球:打球の飛距離や球速は、下半身の筋力+上半身のパワー
-
サッカー:シュートやダッシュの爆発力
-
陸上短距離:スタート加速やフィニッシュスピード
-
バスケ・バレー:ジャンプの高さと速さ
-
柔道・ラグビー:相手との接触やタックルの強さ
👉 どの競技も「筋力とパワーの両立」が成果を左右します。
👪 保護者の方へ
「筋トレ=大人向け」と思われがちですが、成長期の子どもにとっても 正しい方法での筋力・パワートレーニングは安全かつ効果的 です。
むしろ土台を築くことで、ケガを防ぎ、あらゆるスポーツに適応できる体を育てられます。
✅ まとめ
-
Strength=最大筋力、Power=力×速度の爆発力
-
F-V曲線とRFDを意識することが競技力に直結
-
高重量・軽負荷・中間負荷をバランスよく取り入れることが重要
-
野球・サッカー・陸上・バスケ・柔道など、全スポーツに必須
👉 PHYSICAL MONSTER ACADEMYでは、成長段階に応じて筋力とパワーを段階的に育成し、子どもたちが「速く・強く・しなやかに動ける」体をつくるサポートをしています。
タグ: バレー, 柔道, 子ども, 筋トレ, サッカー, 野球, 陸上, バスケ, パフォーマンス, 体, スピード, ケガ, パワー, 筋力, スポーツ
🏃 Movement Skills ― 走る・切り返す・方向転換の技術
スポーツにおけるパフォーマンスを大きく左右するのは、単なる筋力や持久力だけではありません。
「走る」「止まる」「切り返す」「方向転換する」 といった Movement Skills(動きの技術) が土台となり、あらゆる競技力の差を生み出します。
🔬 Movement Skillsとは?
Movement Skillsは「基本動作スキル」の集合体であり、スポーツ特異的な技術の土台になります。
代表的には以下の能力が挙げられます。
-
スプリント(加速・最高速)
-
減速(ブレーキング)
-
方向転換(Change of Direction, COD)
-
アジリティ(Agility:反応を伴う方向転換)
👉 これらは単発ではなく、「走る→止まる→切り返す→再加速」と連続して発揮されることが多く、効率的に習得する必要があります。
📚 出典:Sheppard & Young (2006), Sports Medicine
⚡ なぜ重要か?
-
競技パフォーマンスの向上
短距離走・サッカーの切り返し・バスケットのディフェンスなど、多くのスポーツは「速く動き、素早く止まり、再び動く」能力が勝敗を分けます。 -
ケガ予防
方向転換や減速での動作不良は、特に膝前十字靭帯(ACL)の損傷リスクを高めます。
正しいMovement Skillsを学ぶことで、障害の予防につながります。 -
神経系の発達
成長期に多様な動きを経験することで、神経系の運動プログラムが強化され、生涯の運動能力の基盤となります。
📚 出典:Faigenbaum & Myer (2010), British Journal of Sports Medicine
🏋️ トレーニング例
-
スプリントドリル:Aスキップ、加速ダッシュ
-
減速ドリル:10mダッシュからの急停止、スティック動作
-
方向転換ドリル:プロアジリティシャトル、505テスト動作練習
-
アジリティドリル:パートナー反応ステップ、ライト反応ドリル
👉 重要なのは「無意識で再現できる」まで繰り返し、さまざまな文脈で練習することです。
⚽ スポーツ応用
-
野球:盗塁スタート、打球反応
-
サッカー:1対1での切り返し・スプリント
-
バスケット:ディフェンスのスライドと方向転換
-
ラグビー:接触後の再加速
-
陸上短距離:スタートダッシュからの加速局面
👪 保護者の方へ
「走るのが遅い」「切り返しが苦手」というのは、筋力不足だけが原因ではありません。
多くの場合、動作の仕組みを知らないまま繰り返していることが原因です。
👉 子どもに必要なのは、
-
正しい動作パターンを学ぶこと
-
多様な動きの経験を積むこと
-
成長に合わせて段階的に進めること
です。
✅ まとめ
-
Movement Skills=「走る・止まる・切り返す・方向転換」の基礎技術
-
パフォーマンス向上・ケガ予防・神経系発達に直結
-
成長期に多様な動きを学ぶことが一生の財産になる
-
野球・サッカー・陸上・バスケ・ラグビーなど、全競技で必須
👉 PHYSICAL MONSTER ACADEMYでは、年齢や発達段階に合わせてMovement Skillsを体系的に指導し、子どもたちの「強く・速く・安全に動ける体」を育んでいます。
タグ: ケガ予防, サッカー, 野球, 陸上, バスケ, パフォーマンス, 成長, 持久力, 走る, ケガ, 筋力, スポーツ
子どもの筋トレにおける「追い込み」について💪
トレーニングの世界でよく聞く「追い込み」。
「動けなくなるまでやること」と思われがちですが、実はもっと広い意味があります✨
🔍 「追い込み」とは?
-
🏋️♂️ 筋肉が疲れて「きつい」と感じること
-
🔁 繰り返して運動量を増やすこと
-
🔥 エネルギーをたくさん使うこと
-
✅ 正しいフォームで「これ以上できない」ところまで行うこと
-
💡 「頑張った!」という心理的な努力
👉 つまり「追い込み」とは 無理をさせることではなく、体と心に適度な刺激を与えること です。
🧩 筋肉が成長する仕組み
-
⚡ 筋肉は「疲れたから」大きくなるわけではありません。
-
🎯 大切なのは より多くの筋肉を働かせること。
-
トレーニングをすると、最初に使っていた筋肉が疲れ → 新しい筋肉が呼び起こされます。
-
この 「新しい筋肉の動員」 が成長のカギ🔑です。
❓ 限界までやる必要はある?
-
🚫 「もう一回もできない!」までやる必要はありません。
-
👍 ポイントは “あと少しできる”くらいまで頑張ること。
-
その方が 安全で効果的 に筋肉を育てられます。
👦 子どもにとっての「追い込み」
-
大人のように極限までやる必要はなし🙅♂️
-
子どもには 「ちょっときついけど頑張れた!」 という経験が大切🌱
-
それが…
-
🌟 達成感
-
💪 やり抜く力
-
🧍♂️ 正しい体の使い方
につながります。
-
✅ まとめ
-
「追い込み」とは無理をすることではなく、安全に刺激を与えること。
-
成長には 多くの筋肉を働かせること が大事。
-
限界までやらなくても、“あと少し”の努力で十分効果あり。
-
子どもには、成長段階に合わせた安全な「追い込み」が必要👶➡👦➡🧑
当アカデミーでは、無理のない範囲で 科学的に安全&効果的なトレーニング を行い、子どもたちの成長を全力でサポートしています🙌✨
🏃 Plyometrics ― 走る・跳ぶ力をトレーニング
スポーツで必要な「走る力」「跳ぶ力」を育てるうえで欠かせないのが プライオメトリクス(Plyometrics) です。
これは単なるジャンプ練習ではなく、筋肉・腱の特性と神経系を利用して爆発的な力を発揮するトレーニング法 です。
🔬 SSC(Stretch-Shortening Cycle)とは?
プライオメトリクスの中心となる考え方は SSC(伸張反射)。
-
筋を素早く伸ばす(エキセントリック収縮)
-
直後に縮める(コンセントリック収縮)
👉 これにより「バネのように」力を一気に解放できます。
📚 Komi (2000), Strength and Power in Sport
🧩 マッスルスラック(Muscle Slack)とは?
筋肉はただ力を出すだけでなく、収縮前に“たるみ(Slack)”を取る時間があることが知られています。
-
Slackが大きい=力を出すまでに時間がかかる
-
Slackが小さい=すぐに力を伝えられる
👉 プライオメトリクスは、この「Slackを素早く処理する能力」を高める点でも重要です。
例
-
静止した状態からのスクワットジャンプ → Slack処理能力が試される
-
連続ジャンプやドロップジャンプ → SSCによる弾性利用が中心
つまり、SSCを使う種目と、Slack処理を狙う種目を両方行うことで、爆発的パワーの土台が完成します。
📚 van Hooren & Zolotarjova (2017), Sports Medicine
⚡ Plyometricsの効果
-
爆発的パワーの向上(ジャンプ高・加速力)
-
神経系の発達(速筋動員・反応速度改善)
-
力の立ち上がり率(RFD)の強化
-
着地動作の習得によるケガ予防
📊 科学的ガイドライン(De Villarreal et al., 2009)
プライオメトリクスの実施基準(成人を対象とした研究ベース)は以下です。
スピードストレングス目的(週2回)
-
頻度:週2回
-
量:40–60コンタクト/セッション(≦120/週)
-
強度:4–6回 × 2–3セット
-
休息:1–3分(セット間)、72時間(セッション間)
アクティベーション目的(週4回)
-
頻度:週4回
-
量:20–30コンタクト/セッション(≦120/週)
-
強度:4–6回 × 1–2セット
-
休息:1–2分(セット間)、24時間(セッション間)
👉 子どもにはこの基準を調整し、着地の習得と質の管理を最優先します。
⚽ スポーツ応用例
-
野球:投球・打撃で下半身の反力を効率的に伝える
-
サッカー:シュートやジャンプヘディングの爆発力
-
陸上短距離:スタートダッシュや加速の強化
-
バスケ・バレー:高く跳び、安定して着地する力
-
柔道・ラグビー・剣道:コンタクト直後に崩れない踏ん張り
👪 保護者の方へ
「たくさんジャンプすれば跳べるようになる」と思われがちですが、実際は “ジャンプの質”をどう管理するか が大切です。
-
SSCを活かすトレーニング(反発力の利用)
-
マッスルスラックを処理するトレーニング(反動なしで爆発的に動く)
👉 この両方を経験することで、子どもは「速く・強く・安全に動ける体」を手に入れます。
✅ まとめ
-
Plyometrics=SSCとマッスルスラックの両方を鍛えるトレーニング
-
SSC:弾性エネルギーを利用した効率的な力発揮
-
マッスルスラック:力を“ゼロから立ち上げる”能力
-
科学的ガイドラインに基づき、回数・休息を調整することが必須
-
子どもの成長段階に応じて適切に導入することで、あらゆるスポーツに直結
👉 PHYSICAL MONSTER ACADEMYでは、この両面をバランスよく取り入れ、子どもたちが 「走る・跳ぶ・ぶつかる」動作をより強く、より安全に実行できる体 を育てています。
タグ: バネ, バレー, 跳ぶ, 柔道, 剣道, ラグビー, 子ども, サッカー, 野球, 陸上, バスケ, スピード, 走る, トレーニング, パワー, 筋力, スポーツ
👩👩👧👦 子どもにとっての親は「Boss」?それとも「Leader」?
1. リーダーシップとは?
リーダーシップは「役職」や「権限」ではありません。
Barrow(1977)はこう定義しています。
👉「目標を達成するために組織されたグループに対して影響を与える個人の行動過程」
つまり、リーダーは特別な人だけがなるのではなく、誰もが状況に応じてリーダーになれるということです。
元Meta COOのシェリル・サンドバーグも、
💬「リーダーシップとは、リーダーが不在となってもその影響が続くこと」と語っています。
2. BossとLeaderの違い ⚖️
同じ「指導」でも、関わり方には大きな差があります。
-
Boss 👉 命令する・支配する・恐怖で動かす
-
Leader 👉 問いかける・一緒に考える・可能性を引き出す
Bossは「自分のために」人を動かし、
Leaderは「相手の成長のために」力を注ぎます✨
3. 子育てに置きかえると… 👨👩👧
子育ての場面で、つい
「早くしなさい!💢」
「なんでできないの?😤」
と言ってしまうこと、ありませんか?
実はこれ、社会人として出会った「嫌な上司(Boss)」とそっくりなんです。
皆さんも、Boss的な上司に理不尽さや不快感を覚えた経験があるはず。
その経験を子育てに活かすなら――
👉 「子どもに対してBossにならない」
という意識がとても大切です。
4. Leader的な関わりのポイント 🌟
親は子どもにとって一番身近な「指導者」。
だからこそ、Leader的な関わりが、挑戦心や自信を育てます。
-
❓ 命令より問いかけを
「早くやりなさい!」より「どうすれば早くできそう?」 -
🤝 失敗を責めない
「なんで失敗したの!」より「次はどうしたらうまくいくかな?」 -
👀 プロセスを認める
結果だけでなく「ここまで頑張ったね!」を伝える -
🚀 可能性を信じる
「どうせ無理」ではなく「少しずつ挑戦してみよう」
5. 科学が示すリーダーシップの力
Bass(1985)は「変革型リーダーシップ」を提唱しました。
これは、命令や報酬ではなく 感情やモチベーションに訴えかけ、可能性を最大限に引き出すスタイルです。
その特徴は次の4つ。
-
理想的な影響力(ロールモデルになる)
-
モチベーションを鼓舞する
-
思考を刺激し、新しい発想を生む
-
個々への配慮を欠かさない
これはまさに、子育てにおける「理想の親」の姿と重なります🌱
🎯 まとめ
-
Bossは命令して従わせる 💢
-
Leaderは寄り添い、成長を支える 🌱
-
親がLeaderであることで、子どもは安心して挑戦できる ✨
👉 子どもにとって理想の親は「Boss」ではなく「Leader」。
日常の声かけをちょっと変えるだけで、未来への大きな力につながります💪😊
タグ: 子ども
子どもの成長を支える「信頼関係のコミュニケーション」
スポーツや学びの場で成果を出すために欠かせないのが「トレーニング」ですが、実はそれ以上に大切なのが コミュニケーション です。子どもと指導者、子どもと保護者の間に信頼関係があることで、安心して挑戦できる環境が生まれます。
今回は、最新の心理学や教育学の視点から「信頼を育てるコミュニケーション」について整理してみます。
1. コミュニケーションとは?📢
コミュニケーションとは「意味を理解し、共有するプロセス」(Pearson & Nelson, 2000)。
単に言葉を伝えるだけでなく、「相手の気持ちや考えを一緒に確かめていく」ことが本質です。
2. 信頼関係を築く4つのポイント🤝
研究(Hardcastle & Taylor, 2014)では、信頼やモチベーションを高めるコミュニケーションの要素として、次の4つが示されています。
-
共感力を持つ
「わかるよ」「大変だったね」と、相手の気持ちを受け止める。 -
ギャップをつくる
現状と理想の違いを確認し、「どうすれば理想に近づけるか」を一緒に考える。 -
行動の継続を支える
説明や押し付けではなく、「続けたい」と思える環境を整える。 -
自己効力感を育てる
「できそう」「やれるかも」という気持ちを引き出すことで、挑戦する力を強める。
3. 効果的なコミュニケーションスキル🛠️
具体的にどんな声かけが効果的か、研究からヒントをまとめます。
-
オープンな質問をする
「どうしたい?」「どんなふうに感じた?」と自由に話せる質問を投げる。 -
感謝を伝える
「やってくれてありがとう」と小さなことでも感謝を言葉にする。 -
リフレクティブリスニング(繰り返し返す聴き方)
「こう思ってるんだね」と相手の言葉をそのまま返す。 -
相手の言葉でまとめる
専門用語ではなく、本人の表現を使って会話を整理する。
4. 継続につながる工夫🚀
運動や学習を「続ける」ためのコミュニケーションでは、次の点がポイントです。
-
どんな変化を望んでいるかを聞く
例:「もっと体力をつけたい?」「リラックスしたい?」 -
準備・重要性・自信について確認する
例:「この練習を続けること、どのくらい大事だと思う?」「自信はどのくらいある?」 -
選択を整理して見える化する
「変える/変えない」それぞれの良い点・良くない点を一緒に考える。
まとめ🎯
-
コミュニケーションは「意味を理解し、共有するプロセス」
-
信頼関係を築くには、共感・ギャップ・継続支援・自己効力感 が大切
-
オープンな質問や感謝の言葉が、子どものやる気を引き出す
-
継続のためには「選択を整理し、自分で決める」プロセスをサポートする
🤸 Mobility ― 子どもの体をしなやかにする
🔄 Mobilityとは?
Mobility(モビリティ)とは「関節が適切な範囲で、スムーズに動ける能力」を指します。
単なる柔軟性(Flexibility)とは違い、筋力・神経制御・関節構造が組み合わさった“動ける柔らかさ”のことです。
🧩 Mobilityが不足すると?
-
股関節が硬い → 腰椎や膝で代償 → 腰痛や膝のケガにつながる
-
足首の背屈制限 → スクワットやジャンプのフォームが崩れる
-
胸椎が回らない → 投球や打撃で肩・肘に過剰な負担
つまり「動くべき関節が動かない」と、他の関節が無理に動いてケガの原因になります。
📚 出典:Cook (2010). Movement: Functional Movement Systems
⚽ スポーツへの応用
-
野球・テニス:胸椎と肩関節の可動域が投球やサーブの伸びに直結
-
サッカー:股関節・足首のモビリティがシュートや切り返し動作をスムーズに
-
陸上短距離:足首の背屈可動域がスタートと加速局面を支える
-
バスケット・バレー:股関節や足首の可動性がジャンプや着地の安定性を高める
👪 保護者の方へ
「体が硬い=ケガが多い」子は少なくありません。
成長期にしっかりモビリティを確保することで、
✅ ケガを防ぐ
✅ 基本動作をスムーズにする
✅ スポーツの技術習得を早める
といった効果が期待できます。
柔らかさはストレッチだけでなく、動きを通じて“使える柔らかさ”を育てることが大切です。
✅ まとめ
-
Mobility=“動ける柔らかさ”
-
不足するとケガやフォーム崩れにつながる
-
競技パフォーマンスに直結
-
成長期にしっかり整えることが重要
👉 PHYSICAL MONSTER ACADEMYでは、股関節・足首・胸椎など「動くべき関節」のモビリティを重点的に育成し、子どもたちが しなやかに、思い切り動ける体 をサポートしています。
タグ: ストレッチ, テニス, サッカー, 野球, 陸上, バスケ, パフォーマンス, 成長, ジャンプ, ケガ, 筋力, スポーツ
観念が“予測”を変え、動きが変わる🧠➡️🏃♀️
子どもたちの動きや学びは、単に筋肉や神経だけで決まるものではありません。
実は「観念(ものの見方・考え方)」が、脳の“予測”に影響を与え、行動そのものを変えてしまいます。
1. 脳は「予測」で動いている🧩
脳は、動く前に「これからどうなるか」を予測します。
その予測をもとに体を動かし、結果とズレがあれば修正し、また次の予測につなげる。
この予測 → 実行 → 誤差 → 修正 → 再予測のループを繰り返すことで、動きは洗練されていきます。
2. 観念が予測を左右する🧠
予測の土台になっている「内部モデル」は、これまでの経験や感覚だけでなく、**観念(考えの持ち方)**の影響を強く受けます。
たとえば——
膝に痛みを感じた経験がある子どもが「また痛くなるかもしれない」と思い込むと、その観念が予測を歪めます。
結果、本当は動ける場面でも膝を固めてしまい、動きがぎこちなくなるのです。
逆に「少しずつなら大丈夫」「できるところからやってみよう」という観念を持つと、予測が前向きに更新され、動きは自然にスムーズになります。
3. 探索(Play)が観念を更新する🌱
子どもが自分から試して、感覚を確かめる「探索(Play)」は、観念を現実に即してアップデートしていく大切な行為です。
「できた!」「ちょっと違った!」という体験を重ねることで、内部モデルが書き換えられ、次の予測がより正確になります。
4. 最適な学びの場:Safe × Uncertain🛡️❓
学びの環境は次の4つに整理できます。
-
Safe × Certain(安全・確実)
安心できるが、新しい発見が少ない。 -
Safe × Uncertain(安全・不確実)
安全を感じつつも、挑戦や探索を受け入れやすく、学びと成長の機会が多い。 -
Unsafe × Certain(危険・確実)
リスクが高く、安全性に脅威。学びには不適。 -
Unsafe × Uncertain(危険・不確実)
危険で予測不能。環境として望ましくない。
結論として——
安全性を確保しながら、結果が一つに固定されない課題を与えることが、脳の予測力を磨き、観念を健やかに更新していきます。
5. ご家庭でできるサポート🏡
-
安心感を先に作る:「見てるから大丈夫」と声をかける
-
やり方を一つに決めない:複数の工夫を試せるようにする
-
問いかけをする:「今どんなふうに感じた?」と聞いて、自分の感覚と考えをつなげる
-
小さな差を比べる:ゆっくり/速く、広く/狭くなど条件を変えて体験させる
-
失敗を前向きに:「そのやり方も試したんだね」と修正の過程を認める
まとめ🎯
-
脳は予測で動いている
-
観念は予測に大きな影響を与える
-
膝の痛みのように「また痛いかも」という観念は動きを固める
-
一方で「できるところから」という観念は予測を前向きにする
-
安全で不確実な環境(Safe × Uncertain)が、最も成長を促す学びの場になる
子どもたちが挑戦を楽しみ、失敗を糧にできるように、安心感とちょっとした不確実性のある環境を日常に取り入れていきましょう✨
子どもの成長を支える「動作教育」とは?👟✨
みなさんは「動作教育」という言葉を聞いたことがありますか?
これは単に「体を動かす練習」ではなく、動きを通して心や人間性まで育てる教育のことを指します。
動作教育ってなに?🤔
動作教育は、体の動きだけを鍛えるものではありません。
-
感覚(見る・聞く・触れるなど)
-
認知(考える・判断する)
を使って体を動かし、子どもが 自分らしく成長していく力 を育む教育法です。
動きの経験を通して「心の健康」「社会での関わり方」にもつながるのが特徴です。
どうして大切なの?🌱
子どもたちは、スポーツや勉強だけでなく、日常の中でたくさんのプレッシャーや失敗を経験します。
そのとき「動きを通じて自分の感覚と向き合える子」は…
-
ケガからの回復が早い
-
安定したパフォーマンスを発揮できる
-
失敗を「次のチャレンジ」に変えられる
つまり、強い心と体をつくる土台になるのです。
「動き=環境との会話」💬
動作教育では、動きを 自分と環境とのコミュニケーション と考えます。
例えば…
-
サッカーでボールの速さを感じて動く ⚽
-
雨が降りそうだから傘を持って出かける 🌧️
-
ケガをしたときに「どう動かすか」だけでなく「どう感じるか」を大切にする
こうした経験の積み重ねが、子どもの「自己理解」や「社会性」を育みます。
保護者ができるサポート💡
ご家庭でもできるサポートはとてもシンプルです。
-
「動き」を楽しむ場を用意する(遊び・運動・外遊び)
-
できたことをしっかり認めてあげる 👍
-
失敗しても「次につながるね」と前向きな言葉をかける 🌟
-
体の感覚に耳を傾けるよう促す(「どんな感じがする?」と聞いてみる)
まとめ
動作教育は、ただの運動トレーニングではなく、
子どもが生きる力を身につけるための“心と体の教育” です。
日常の小さな遊びや動きが、子どもの未来をつくる大きな一歩になります。
ぜひご家庭でも「動きと感覚」を大切にしながら、お子さんの成長を応援してください😊💪