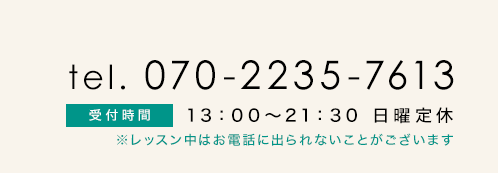レジリエンス:ストレスやプレッシャーを力に変える方法💪🌱
スポーツや勉強、日常生活の中で、子どもたちは必ず「失敗」や「プレッシャー」に直面します。
そのときに大切になるのが レジリエンス(心理的レジリエンス) です。
レジリエンスとは?🤔
レジリエンスは「逆境やストレスがあっても前に進み続ける力」を意味します。
性格や才能ではなく、トレーニングで高められるスキル であることが大きなポイントです。
🔹 困難な状況でも自分を守る力 🛡️
🔹 普段の心の働きを保ち続ける力 🧠
🔹 強みを発揮し、挑戦を続ける行動 🚀
レジリエンスが必要な場面📌
レジリエンスは、スポーツだけでなくライフスキル全般に直結します。
例えば…
💤 メンタルヘルス(不安・ストレス・睡眠)
🌪️ 失敗や挫折からの立ち直り
🔥 モチベーション(練習・試合)
🎯 目標達成・学習
🙌 自己効力感(「自分ならできる」という感覚)
子どもたちが挑戦を楽しみながら成長するために不可欠な力です✨
鍛える方法(実践のヒント)🛠️
👨👩👧👦 人との関係を大切にする
助けを求めたり、仲間と支え合うことが回復力の源になります。
🔍 自分を理解する
得意・苦手、価値観を知ることは、自信の土台となります。
✅ できたことを確認する
小さな成功を「できた!✨」と認める習慣がモチベーションを支えます。
📈 失敗を前向きにとらえる
失敗を「終わり」ではなく「次のステップ」に変える視点を持つこと。
🎯 目標を持ち、意味を見出す
「なぜ頑張るのか?」という目的意識が心を強くします。
😌 不安やイライラを自分で止める
(例)気づき → 深呼吸 → 行動を切り替える、という練習を。
🌞 楽観的に物事をとらえる
「問題」ではなく「課題」と考えるだけで心の余裕が変わります。
🌱 「まだこれから」を受け入れる
未完成でも大丈夫。「Power of Yet(まだこれから)」が成長を促します。
🔄 適応力を高める
変化を恐れず、新しい考え方や行動を取り入れること。
⏳ 長期的な視点を持つ
今の結果に一喜一憂せず、人生の大きな流れの中で成長をとらえること。
まとめ📝
レジリエンスは、生まれつきの才能ではなく 「鍛えられる力」 です。
子どもたちが失敗を恐れず、挑戦を楽しみ続けられるように、日常の中で少しずつ「心のトレーニング」を取り入れていきましょう💪🌟
子どもの「恐怖」と「痛み」の関係を知っていますか?
こんにちは!PHYSICAL MONSTER ACADEMYです😊
今日は、ちょっと専門的だけど実はとても身近なテーマ―― 「恐怖」と「痛み」 の関係についてお話しします。
💭 恐怖が行動を変える
ケガや失敗を経験した子どもは、痛みだけでなく 「また痛いかもしれない」 という恐怖心を抱きます。
この恐怖が強すぎると…
-
ケガをした足をかばって走らない
-
転ぶのが怖くてジャンプを避ける
-
「また痛くなるかも」と思ってチャレンジしない
こうした 恐怖回避行動 が増えてしまいます。
一見「安全」そうですが、実は体を動かす機会を減らし、筋力や柔軟性の低下につながることもあります。
🏃♀️ 動くのが怖い…Kinesiophobia(動作恐怖)
スポーツ医学の分野では、動くこと自体に強い恐怖を感じることを Kinesiophobia(動作恐怖) と呼びます。
研究によると、この恐怖心が強い人ほど…
-
リハビリの成果が出にくい
-
ケガからの回復が遅れる
といった影響が報告されています。
🧠 恐怖は「痛みの感じ方」まで変える
恐怖や不安は、単なる気持ちの問題ではなく 痛みの感じ方そのもの に影響します。
-
実際には冷たい刺激なのに「これはすごく熱いよ」と言われると、人は “やけどするかも” と恐怖を連想し、より強い痛みを感じてしまう 実験があります。
-
慢性腰痛の患者さんでは、恐怖心が強いと筋肉を固めすぎて歩行がぎこちなくなることがわかっています。
つまり「痛みが出るかも」という予測や恐怖が、動きや感じ方を増幅させてしまうのです。
💡 子どもの恐怖にどう向き合う?
保護者の方ができることは、とてもシンプルです。
✅ 安心させる言葉がけ
-
「大丈夫、少しずつできるよ」
-
否定せずに、前向きな言葉を選ぶ
✅ 成功体験を積ませる
-
小さな動作でも「できた!」を感じさせる
-
失敗しても励まし、チャレンジを続けさせる
✅ 正しい知識を伝える
-
「必要以上に安静にしすぎると、回復が遅れてしまうことがある」
-
「専門家の指導を受けながら、少しずつ体を動かすことがリハビリにつながる」
🌈 まとめ
子どもの「恐怖」は自然な感情ですが、強すぎると回復や成長の妨げになります。
だからこそ、保護者の温かい言葉やサポートで「怖い」から「やってみよう!」へと気持ちを切り替えられるようにしてあげることが大切です😊
PHYSICAL MONSTER ACADEMYでは、子どもたちが安心してチャレンジできる環境を整え、心と体の成長を全力でサポートしています💪✨
🌟 自己効力感ってなに?子どもの「できる!」を育てるために大切なこと
みなさんは「自己効力感(じここうりょくかん)」という言葉をご存じですか?
ちょっとむずかしい表現ですが、これは 「ある場面で、自分はきっとやり遂げられる!」という確信 のことを指します。
よく「自己効力感=自信」と紹介されることがありますが、実は少し違います。
自信は漠然とした「できるかも」という感覚ですが、自己効力感はもっと具体的。
「跳び箱の6段を跳べる!」「逆上がりができる!」といった 特定の課題に対して“できる”と思える気持ち なんです 💡。
🏅 自己効力感を高める一番のカギは「達成体験」
心理学者バンデューラによると、自己効力感を育てるうえで一番大切なのは 達成体験(できた!という成功体験) です。
-
はじめは失敗しても、練習を重ねて「できた!」につなげる
-
小さな成功を積み重ねることで「やればできるんだ」という感覚が強くなる
これが自己効力感の土台になります。
ですから、お子さんにとっては「できないことに挑戦 → 少しずつ上達 → できた!」というステップがとても大事なんです✨。
👀 モデリング(まねして学ぶ力)
「お兄ちゃんが跳べたから、ぼくも跳べそう!」
「友だちが頑張ってるから、自分もできるかも!」
こうした 他人の成功体験を見て学ぶ(モデリング) も、自己効力感を育てる重要なポイントです。
子どもたちは身近なモデルから勇気をもらいます。
💬 言葉がけの力
「もう少しでできるよ!」「よく頑張ったね!」
コーチや親からの前向きな言葉も、自己効力感を後押しします。
逆に「なんでできないの?」といった言葉は、せっかく芽生えたやる気をしぼませてしまうことも…。
声かけはシンプルですが、とても大きな力を持っています🌱。
💓 感情や体の感じ方も関係する
試合前のドキドキを「不安だからダメかも」ととらえるか、
「よし!集中できている証拠」ととらえるかで、自己効力感は変わります。
同じ身体反応でも、ポジティブにとらえれば力になります。
親御さんが「緊張してるね、でもそれは頑張る準備ができてる証拠だよ😊」と声をかけてあげるのも効果的です。
🌱 まとめ
-
自己効力感は「自信」とは違い、特定の場面で“できる!”と思える感覚
-
一番大切なのは「達成体験」=小さな成功を積み重ねること
-
まわりのモデルや前向きな言葉がけも大きな支えになる
-
ドキドキや緊張をポジティブにとらえる工夫もポイント
お子さんが「やればできる!」と感じられる体験を積むことで、チャレンジする気持ちも伸びていきます。
その先に、スポーツだけでなく勉強や生活でも「前向きに挑戦できる力」が育っていくのです 🌈。
子どもの目標達成を応援するには? 🎯✨
みなさんのお子さんは、スポーツや勉強で「こうなりたい!」という目標を持っていますか?
私たち大人ができる一番のサポートは、その目標に向かう意欲=モチベーションをうまく引き出してあげることです💪
1️⃣ 目標の意味を一緒に考える
「速く走れるようになりたい」「試合で点を取りたい」など、子どもたちはいろいろな目標を口にします。
そのときに大切なのは、ただ「いいね!」と答えるだけでなく、
-
その目標の意味は?
-
なぜその目標なのか?
-
何のための目標なのか?
を一緒に考えてあげることです👀✨
こうした問いかけが、子どもにとって「自分で選んだ目標だ!」という感覚を強め、頑張る力につながります。
2️⃣ 子どもをよく知ること
一人ひとりの性格や価値観を理解することも欠かせません。
「お友だちと一緒に頑張りたいタイプ」なのか「一人でコツコツ努力するのが好きなタイプ」なのかによって、サポートの仕方も変わります👦👧
3️⃣ 達成しやすい目標の立て方
研究では「結果目標」よりも「過程や行動に注目した目標」が効果的だといわれています📚
例えば…
❌ 「大会で優勝する!」
⭕ 「毎日10分ドリブル練習を続ける!」
また、短期(6週間くらい)と長期(1年くらい)の両方を組み合わせて目標を立てると、継続の力になります📅
4️⃣ モチベーションを高める3つのカギ 🔑
子どもたちが「やらされている」ではなく「やりたい!」と思えるには、この3つがポイントです。
-
自主性(Autonomy):自分で選んでいる感覚
-
有能感(Competence):上達した!できた!という実感
-
関係性(Relatedness):仲間や家族とのつながり
この3つが満たされると、モチベーションはグンと高まります🚀
5️⃣ 内発的モチベーションと外発的モチベーション 🌱🎁
-
内発的モチベーション:
子ども自身が「やりたい!」「楽しい!」と思って行動する気持ち。
例:新しい技を覚えるとワクワクする、体を動かすと気持ちいい。 -
外発的モチベーション:
褒められる、ご褒美がある、叱られないためにやるといった「外からの刺激」によるやる気。
例:試合に勝ったら親に褒められる、宿題をしないと叱られるからやる。
👉 外発的な要素も短期的には役立ちますが、本当に力になるのは内発的モチベーション。
子どもが「やらされている」から「やりたい!」に変わるように、声かけや環境を工夫することが大切です🌟
まとめ 🌟
大切なのは「子ども自身が持つ目標や価値観」に寄り添うこと。
親が正しい指導やアドバイスをするだけでなく、「なぜその目標なのか?」を一緒に考え、応援する姿勢が子どものやる気を育てます。
小さな成功体験を積み重ねながら、子どもたちが自分の力で目標に向かって進んでいけるように、私たちもサポートしていきましょう😊🙌
Movement Preparation ― 動きの準備を科学する
🔄 Movement Preparationとは?
「ウォームアップ=体を温める」だけではなく、科学的に体を“動ける状態”へ整えるプロセスです。
PHYSICAL MONSTER ACADEMYでは、以下の 5つのステップ に分けて実施しています。
① ジェネラルムーブメント(General Movement)
-
軽いランやスキップ、ラダーなどで全身の血流を促す
-
心拍数を上げ、体温を高める
👉 「エンジンをかける」イメージ
② ダイナミックストレッチ(Dynamic Stretch)
-
動きを伴ったストレッチで、股関節や肩関節などを広く動かす
-
静的ストレッチと違い、筋温を下げずに可動域を拡大
👉 「動きながら柔らかさを引き出す」ステップ
③ マッスルアクティベーション(Muscle Activation)
-
バンドや自重で小さな筋群を目覚めさせる
-
例:臀筋、肩甲帯まわり、体幹の深層筋
👉 「眠っている筋肉のスイッチを入れる」工程
④ ムーブメントインテグレーション(Movement Integration)
-
実際のスポーツ動作に近いパターンを組み合わせる
-
例:ランジ+ツイスト、ジャンプ+着地
👉 「動きをつなげて全身を協調させる」段階
⑤ ニューラルアクティベーション(Neural Activation)
-
短いダッシュ、リアクションドリル、ジャンプなどで神経系を刺激
-
脳と体の反応スピードを高め、爆発的な動きに備える
👉 「試合や練習にスイッチを入れる」仕上げ
⚽ スポーツへの応用
-
野球:肩肘に負担をかけずに投球フォームへ入れる
-
サッカー:切り返しやシュートに必要な股関節の柔軟性を確保
-
陸上短距離:スタート前に神経系をオンにして爆発的な加速
-
バスケ・バレー:ジャンプ・着地の安定性を事前にチェック
-
柔道・ラグビー:接触や衝突の準備を体幹から整える
👪 保護者の方へ
「準備運動は軽くやればいい」と思われがちですが、
実はこの 5ステップのMovement Preparation が、子どもの成長期のケガ予防とパフォーマンス向上に直結します。
✅ まとめ
-
Movement Preparation=科学的に体を“動ける状態”へ導く準備
-
5つのステップ(General → Dynamic Stretch → Activation → Integration → Neural)で実施
-
ケガ予防とパフォーマンス向上の両立に不可欠
👉 PHYSICAL MONSTER ACADEMY では、この5ステップを体系的に取り入れ、子どもたちが安心して全力を出せる体を育てています。
タグ: ダッシュ, 筋, バレー, 柔道, 子ども, ストレッチ, サッカー, 野球, 陸上, バスケ, パフォーマンス, 成長, ジャンプ, ケガ, スポーツ
呼吸と姿勢 ― Proximal Stability for Distal Mobility
🌬️ 呼吸と姿勢のつながり
体幹の安定は、呼吸と深く関わっています。
-
横隔膜(天井)
-
腹横筋(壁)
-
多裂筋(背骨の支え)
-
骨盤底筋群(底)
これらの筋肉が協調して働くことでお腹の中に腹圧(IAP)が生まれ、体幹が内側から安定します。
👉 この安定があることで、手足は本来の 可動性(Mobility) を発揮できます。
これが 「Proximal Stability for Distal Mobility(近位の安定なくして遠位の可動性なし)」 という考え方です。
🛡️ なぜ子どもに大切?
-
体幹が不安定なままでは、足や腕の力を十分に発揮できません。
-
姿勢が崩れると、走る・跳ぶ・投げるなどの動作にブレが出やすくなります。
-
呼吸を通じて腹圧を高め、体幹を安定させることで、スムーズでケガをしにくい動きにつながります。
👀 「体が硬い」ように見える理由
「うちの子は体が硬いんです」と相談されることがあります。
でもその原因が ストレッチ不足とは限りません。
👉 体幹が安定しないと、関節周りの筋肉が余計に緊張してしまい、結果的に可動域が制限されて“硬い”ように見えることがあるのです。
つまり、安定性を整えることで柔らかさが引き出されるケースも多い のです。
⚽ スポーツでの具体例
-
野球:投球・打撃で下半身の力を体幹を通じて腕に伝える
-
サッカー:シュートやドリブルでブレが少なくなる
-
陸上短距離:スタートで地面反力を効率よく推進力に変える
-
バスケ・バレー:ジャンプや着地で腰や膝の負担を減らす
-
柔道・ラグビー:接触プレーでも姿勢が崩れにくい
👪 保護者の方へ
体幹トレーニングというと腹筋運動をイメージしがちですが、実際に重要なのは 呼吸とIAPを通じた体幹の安定性 です。
👉 近位(体幹)が安定することで、
-
手足の可動性が引き出される
-
姿勢が整う
-
パフォーマンスが向上する
-
ケガのリスクも減る
こうした“土台づくり”が、子どもの成長期には欠かせません。
✅ まとめ
-
Proximal Stability for Distal Mobility=「体幹の安定が手足の可動性を引き出す」
-
体が硬く見えるのは、実は安定性不足が原因の場合もある
-
呼吸とIAPを活用した安定づくりが、姿勢・柔軟性・パフォーマンスに直結する
👉 PHYSICAL MONSTER ACADEMY では、この理論をベースに「守れる体幹・動ける体幹」を育て、子どもたちの可能性を最大限に引き出します。
タグ: バレー, 体が硬い, 筋肉, 跳ぶ, 柔道, ストレッチ, 投げる, サッカー, 野球, 陸上, バスケ, パフォーマンス, 走る, 姿勢, ケガ, 体幹
🏃♀️子どものスポーツを強く・安全に!ウォームアップ/プレクーリング/クールダウンの科学
こんにちは!PHYSICAL MONSTER ACADEMYです😊
今日は「アップ(準備運動)って本当に効くの?」「具体的に何をすればいい?」を、最新知見をかみ砕いてご紹介します。保護者の方が安心してお子さんを送り出せるよう、科学的根拠をベースにまとめました。
🔥 ウォームアップは“やり方次第”で効く
ウォームアップの効果は方向性としてプラス。ただし平均では小〜中程度で、中身が競技に合っているかで差が出ます。
-
体温面:筋・腱の粘性低下、神経伝導の向上、酸素放出促進、代謝アップ
-
非体温面:血流・心拍の立ち上げ、心理的スイッチON
-
ポイント:ただ身体を温めるだけでなく、競技に似たドリル・アジリティ・ジャンプを入れると効果が伸びます💡
🛡️ ケガ予防には強い味方
成長期のケガ予防効果ははっきりプラス。アップにジャンプ/バランス/方向転換を組み込むと、足首捻挫や膝(ACL)リスクを下げやすくなります。
結論:「安全に長く続ける」ために、アップは最強の保険。
⚡ アクティベーション(知識紹介:PARE)
研究では「高強度の運動を短時間行うと、7〜10分後に一時的にパフォーマンスが高まる(PARE)」という現象が報告されています。
ただし本番直前にタイミングよく負荷を入れて7〜10分待つという方法は、実際の現場では難しいのが現状です。
👉 そのため、保護者の方が意識する必要はあまりありません。
実際には「短いダッシュやジャンプなど軽い爆発的動作をウォームアップの最後に入れて、気持ちと体をスイッチONする」程度で十分です。
❄️ 暑い時期のプレクーリング
夏場や高温環境では、試合前に体温を少し下げておくと暑さ起因の低下を防ぎやすくなります。
-
方法:氷スラリー摂取、冷却ベスト、顔・頸・体幹の表面冷却など
-
目安:平均で**+5〜7%のパフォーマンス改善**が報告
-
注意:短距離スプリントは悪化の可能性があるため慎重に。持久系・屋外の猛暑試合向け。
🧊 クールダウンの位置づけ
クールダウン(軽い有酸素やストレッチ)は回復や翌日のパフォーマンス改善に対しては小さい〜非有意の報告が多め。ただし——
-
心理的リセット/ルーティン化には有益
-
軽いジョグ+呼吸整え+関節のやさしい可動は◎
-
ストレッチは**「筋肉痛の特効薬」ではない**ことを理解しておくと安心です。
結論:“身体の回復薬”というより“心身を落ち着かせる習慣”として活用。
🔄 Re-Warm-Up(再アップ)は「後半の立ち上がり&終盤」で必須
ハーフタイムに座って休むだけだと、後半の立ち上がりでパフォーマンスが落ちやすいのが定番の落とし穴。
さらに試合終盤は疲労と体温低下が重なり、いっそうパフォーマンス低下が起きやすい局面です。
-
対策:ハーフタイムに軽いジョグ/ジャンプ/短い加速走などアクティブに再アップ
-
目的:体温・神経の“再点火”と集中の再構築
合言葉は**「立ち上がりで落とさない。終盤で踏ん張る。」**
✅ 保護者の方へのまとめ
-
ウォームアップは小〜中程度のパフォーマンス向上+ケガ予防効果大
-
PAREは研究知識として面白いが現場では扱いづらい
👉 実践は「ダッシュやジャンプで気持ちと体をスイッチON」で十分 -
暑熱環境ではプレクーリングが有効(短距離競技は要注意)
-
クールダウンは回復薬ではなく心理的リセット
-
Re-Warm-Upで後半の立ち上がり・終盤を強くする
🌟 保護者の皆さんへ
アップやクールダウンは「ただの準備運動」ではなく、子どもの体を守り、力を発揮させるための科学的なツールです。小さな工夫が、ケガを防ぎ、長くスポーツを楽しむ力につながります💪✨
Got Peers? 仲間がいることの科学的意義 👫⚽️🏃♀️
「早く行きたければひとりで行け。遠くまで行きたければみんなで行け。」
こんなアフリカのことわざがあります。スポーツや学びの場でも、この言葉はとても大切な意味を持っています。今日は、科学的な研究から見えてきた「仲間の存在がもたらす力」についてご紹介します💡
仲間がいると頑張れる!✨
心理学では Social Facilitation(社会的促進) という現象があります。
これは「誰かと一緒にいるとパフォーマンスが上がる」という効果のことです。例えば…
-
一人で歩くよりも、友達と一緒に歩いた方が長く歩ける👟
-
サイクリングも、仲間がいれば自然とスピードが上がる🚴♂️
-
誰かに見られているだけでベンチプレスの重量が伸びる💪
つまり「人の目」や「仲間の存在」そのものが力を引き出す要素になるのです。
幼児期から仲間の影響は大きい 👶🍴🏃♂️
研究では、幼稚園児の「食習慣」と「運動習慣」にも仲間の存在が影響していることがわかっています。
-
子どもは友達が食べるものをまねして食べる🍎
-
仲間が活発に動けば、自分もより活発になる🏃
さらに中高生になると、友達からの影響はさらに大きくなります。
-
お菓子やジュースの選び方も友達次第🥤
-
野菜の摂取量も友達関係に左右される🥦
-
運動の習慣も「誰と一緒にいるか」で決まる⚽️
兄弟姉妹よりも友達の影響が強まるのは、9〜10歳頃から。まさに成長とともに「仲間」の力が大きくなるのです。
仲間が与えるポジティブな効果 🌟
実験でも仲間の効果が数字で示されています。
-
スポッター(補助者)が視界に入るだけで筋トレの重量が上がる
-
観客がいるとパフォーマンスが向上する📣
-
励ましの言葉をもらうだけで、次の日の運動へのモチベーションまで上がる🔥
パーソナルトレーナーの存在や、競争相手との関わりも同様です。「誰かがそばにいる」「見られている」「声をかけてもらえる」——こうした環境が子どもの力を引き出します。
競争相手がいると成長できる 🏃♀️💨
研究では、ライバルの存在がパフォーマンスやモチベーションを高めることも分かっています。
-
一緒に走るとタイムが縮まる
-
「追いつきたい」「抜かされたくない」という気持ちが努力を後押しする
-
自分の限界を超えるきっかけになる
これは Affordance(アフォーダンス)理論 によって説明されます。つまり、環境や相手の存在が「今の自分の行動をどう選ぶか」に直接影響を与えるのです。
仲間の力をどう活かすか? 👨👩👧👦
保護者の皆さんにとって大切なのは、「子どもを良い仲間の中に置いてあげること」です。
-
家族以外の友達と遊ぶ機会を増やす
-
チームスポーツや集団活動に参加させる
-
応援や励ましの声を惜しまない
子どもたちは仲間の中で刺激を受け、自分の限界を広げていきます。時には仲間との競争で、時には仲間からの励ましで、より大きな成長を遂げるのです🌱
セミパーソナルが最適な理由 ✨
こうした研究結果は、私たちが 「セミパーソナルトレーニング」 を採用している理由にもつながります。
-
1対1のパーソナルでは得られない「仲間の力」を最大限活用できる
-
仲間の存在が楽しさを生み、習慣化につながる
-
競争と協力を同時に経験でき、社会性も育まれる
特に子どもにとっては、仲間と一緒に学び、励まし合い、競い合うことが 心と体の成長を加速させるカギ になります。
まとめ 🌈
「仲間がいる」ことは単なる楽しい時間ではなく、科学的にも子どもの成長を支える大きな要素です。
-
仲間がいるから頑張れる
-
仲間がいるから楽しく続けられる
-
仲間がいるから限界を超えられる
そして、これを最大限に活かす形が セミパーソナルトレーニング。
PHYSICAL MONSTER ACADEMY では、子どもたちが仲間とともに成長できる環境を大切にしています。ぜひ一緒に、「仲間と育つ力」を体験してみませんか?😊✨
子どもの「レジリエンス」を育てる 🌈 ― 逆境を力に変えるスポーツの科学
はじめに
子どもがスポーツを続けると、必ず壁にぶつかります。
⚡ 試合でのプレッシャー
⚡ 思うように結果が出ない時期
⚡ 仲間との関係やケガ
こうした「逆境」にどう向き合うかが、子どもの成長を大きく左右します。
この 逆境を力に変える力 を心理学では レジリエンス(Resilience) と呼びます。
逆境はチャンスになる?✨
オリンピック金メダリストを対象とした研究では、多くの選手が「逆境があったから成功できた」と答えています。
特に幼少期の困難は「心の強さ」を育むきっかけになることも。
つまり 逆境=悪いことではなく、成長のきっかけ になるのです。
レジリエンスとは?🧠
レジリエンスとは、
逆境に耐え、乗り越え、適応する力
のこと。
ただ我慢するのではなく、経験を糧にして成長する力です。
レジリエンスが高い子どもは…
✅ 集中力が高い
✅ 失敗から学べる
✅ 不安に強い
という特徴を持ち、勉強や人間関係にも良い影響を与えます。
運動とレジリエンス ⚽🏃♀️
中高生818名を対象とした研究では、運動を習慣的に行っている子ほどレジリエンスが高い と分かりました。
思春期の運動は「心の土台」を作るうえで欠かせないのです。
チームで育まれるレジリエンス 🤝
676名のサッカー選手を対象とした調査では、
-
個人のレジリエンスが高い → プレッシャー下で力を発揮
-
チームのレジリエンスが高い → 成績に直結
さらに、エリート選手の研究からは、
🌟 リーダーシップ
🌟 失敗から学ぶ姿勢
🌟 仲間の支え合い
🌟 チームの一体感
が、チーム全体のレジリエンスを高める要因であることも示されています。
個人競技では「心の粘り強さ」がカギ 🏊♂️
一方、陸上や水泳などの個人競技では メンタルタフネス(心の強さ) が特に重要。
トレイルランナー307名を対象とした研究では、
「メンタルタフネス → レジリエンス → パフォーマンス」
という流れが確認されました。
つまり、個人競技では“心の粘り強さ”そのものが結果を左右する のです。
家庭でできること 🏡
レジリエンスは「家庭での関わり方」でも大きく育ちます。
✅ 失敗を責めず「学び」に変える声かけ
✅ 結果より努力の過程を認める
✅ どんな時も受け止める安心できる家庭環境
✅ 小さな挑戦を日常に取り入れる
「失敗しても大丈夫、そこから学べるよ」
そう伝えられる家庭こそが、子どもの未来を支える最高の環境です。
まとめ 🌈
-
逆境は子どもの成長のチャンス
-
運動は心の土台をつくる
-
チームでは「結束力」、個人競技では「心の強さ」が大切
-
家庭の支えが子どものレジリエンスを育む
PHYSICAL MONSTER ACADEMYでは、科学的に裏付けられたトレーニングを通して、子どもたちが 「逆境を力に変える力」 を身につけられるようサポートしています💪✨
「やる気が続かないのは“意思”のせいじゃない!科学が解き明かす習慣づけの秘訣」
「毎日コツコツ頑張ろう」と思っても、なぜか三日坊主で終わってしまう…。
子どもに「宿題やりなさい」「運動しなさい」と言っても続かない…。
実はこれは“性格”や“やる気の問題”ではありません。
心理学・行動科学の研究によると、習慣やルーティーンは 文脈(環境) と 自己効力感(自分ならできるという信念) に支えられており、ここが整わないと人は簡単に脱落してしまうのです。
1. 習慣を邪魔する「隠れた敵」
研究では、子どもや大人が Self-regulated(自己調整的) に何かを実践しようとするとき、最大の敵は Motivational Interference(動機づけの妨害) とされています。
例えば…
-
気が散る(Distractibility)
-
他のやりたいことを考えてしまう
-
同時に別のタスクに取り組む(Task switching)
-
悪い気分や持続力の低下
👉 これらが重なると、せっかくの「やる気」が削がれ、行動が止まってしまいます。
2. 習慣と自己効力感の役割
ここで重要になるのが Habits(習慣) と Self-Efficacy(自己効力感) です。
-
習慣(Habits)
繰り返し行動するうちに文脈に結びつき、自動化される行動。
→ 意思の力を必要とせず、自然に実行できる。 -
自己効力感(Self-Efficacy)
「自分はできる」という信念。
→ 研究では、学業成績(GPA)やスポーツの成果、仕事での生産性にも直結することが報告されています。
習慣と自己効力感は相互に影響し合い、行動の持続を強力に支えます。
3. 習慣化の科学 ― 文脈と自動化
最新研究(Gardner, 2012 など)は「習慣は頻度ではなく、自動化(Automaticity)」で強さが決まるとしています。
-
安定した文脈(同じ時間・同じ場所)で繰り返す
-
特定のトリガー(例:帰宅後すぐにストレッチ)に結びつける
👉 これにより「強い習慣」が形成され、意志の消耗を減らします。
4. スポーツにおけるルーティーンの力
習慣と自己効力感は、スポーツの現場でも大きな武器になります。
NBAフリースロー研究
-
プレーオフ14試合、284本のフリースローを分析
-
成功率は ルーティーンを守った選手:83.7% vs 守らなかった選手:71.4%
👉 成功率を左右する重要な要素は「一貫性のあるルーティーン」でした。
ルーティーンの改善余地
さらに大学生を対象にした実験(Moradi, 2015)では、
-
Singer’s Model(5ステップ:準備→イメージ→集中→実行→評価) に基づいたルーティーン
-
自分で考えたルーティーン
-
ルーティーンなし
を比較した結果、ガイドつきのルーティーンが最も効果的でした。
👉 つまり「ルーティーンはただ繰り返せばよいのではなく、科学的に設計できる」ということです。
5. 子どもの習慣づくりに応用するには?
-
固定された文脈:同じ曜日・同じ時間・同じ場所で運動や勉強を行う
-
小さなトリガー:「おやつの前に宿題」「帰宅後に5分運動」など
-
ルーティーン化:毎回同じ流れを守る(準備→実行→振り返り)
-
自己効力感の育成:「できたね」「続けられたね」と成功体験を積ませる
👉 習慣 × 自己効力感 × ルーティーン が揃えば、子どもの「やる気の持続力」は飛躍的に高まります。
結論
やる気が続かないのは、意志の弱さのせいではありません。
科学が示しているのは、文脈・習慣・自己効力感・ルーティーンの仕組みが整えば、誰でも行動を続けられるということです。
PHYSICAL MONSTER ACADEMYでは、この最新科学をトレーニングに活かし、子どもたちが「自然に体を動かす」習慣を作ることを目指しています。
横隔膜と腹圧 ― 子どもの体幹を守る呼吸法
⚡ 横隔膜とは?
横隔膜(diaphragm) は、胸とお腹の間にあるドーム状の筋肉です。
-
息を吸うとき → 横隔膜が下がり、肺に空気が入る
-
息を吐くとき → 横隔膜が上がり、空気が押し出される
👉 呼吸だけでなく、姿勢や体幹の安定にも深く関わる重要な筋肉です。
⚡ 腹圧とは?
腹圧(Intra-Abdominal Pressure, IAP) とは、お腹の中に作られる圧力のこと。
-
横隔膜が下がる
-
お腹周りの筋肉(腹横筋・多裂筋・骨盤底筋)が協調する
-
風船のようにお腹の中に圧がかかり、体幹が安定
👉 腹圧がしっかり働くと、腰や背骨を守りながら力を発揮できます。
🏃 スポーツと腹圧の関係
-
走る・跳ぶ:着地の衝撃から腰や背骨を守る
-
投げる・打つ:体幹が安定することで、下半身の力を上半身に伝えられる
-
方向転換:体幹がブレずに素早く切り返せる
👉 腹圧が弱いと「腰が反る」「体幹がグラつく」ため、ケガのリスクやパフォーマンス低下につながります。
⚽ 子どもに大切な呼吸法
大人のように重いウエイトを持たなくても、呼吸を通じて腹圧を高める練習は子どもにとって安全で効果的です。
簡単なトレーニング例
-
仰向けで寝て、お腹に手を当てる
-
鼻から大きく息を吸って、お腹が膨らむのを感じる
-
息を止めず、軽く「フーッ」と吐きながら腹圧を保つ
👉 「風船をお腹で膨らませるイメージ」で行うとわかりやすいです。
👪 保護者の方へ
「体幹を鍛える」というと腹筋運動を思い浮かべるかもしれません。
しかし実際には、横隔膜を正しく使い、腹圧を高める呼吸法こそが体幹を守る土台です。
👉 子どもの頃から自然に正しい呼吸ができると、
-
ケガをしにくい
-
姿勢が崩れにくい
-
スポーツの力を最大限に発揮できる
といった大きなメリットがあります。
✅ まとめ
-
横隔膜は呼吸だけでなく体幹の安定に関わる筋肉
-
腹圧=お腹の中の圧力 が高まると背骨を守り、力を伝えやすくなる
-
スポーツ動作(走・跳・投・打・切り返し)すべてに腹圧は重要
-
子どもは呼吸法を通じて、自然に腹圧を高める練習ができる
👉 PHYSICAL MONSTER ACADEMY では、呼吸と体幹の安定を重視し、子どもたちの安全で力強い動きを育てています。
Stiffnessと弾性エネルギー ― 走・跳・投・打の効率を高める
⚡ Stiffness(スティフネス)とは?
Stiffness(スティフネス/剛性) とは、関節や筋腱が「外からの力にどれだけ抵抗できるか」を示す性質です。
👉 簡単に言えば、バネの硬さのようなもの。
-
Stiffnessが低すぎる → ふにゃふにゃして力が逃げる
-
Stiffnessが高すぎる → 動きが固くなり、ケガのリスクも増える
理想は「ちょうどいい硬さ」で、地面を押した反力を効率的に利用できる状態です。
⚡ 弾性エネルギーとSSC
筋肉や腱はゴムのように「伸び縮み」してエネルギーを貯めて解放できます。
-
伸びるとき → 弾性エネルギーを一時的に蓄える
-
縮むとき → 蓄えたエネルギーを解放する
この仕組みを Stretch-Shortening Cycle(SSC/伸張-短縮サイクル) と呼び、走・跳の効率を飛躍的に高めます。
👉 例:ジャンプで着地した瞬間に腱や筋肉が伸び → 次の跳躍で解放され、高く跳べる。
🏃 捻転差もSSCの一種
投球や打撃で使われる 捻転差も、SSCの一種です。
-
骨盤と胸郭の回旋に差を作る(=体幹や斜腹筋群が伸ばされる)
-
このとき弾性エネルギーが蓄えられる
-
直後に縮んで爆発的な回旋力を生み、ボールやバットに力を伝える
👉 ジャンプは縦方向のSSC、投球や打撃は回旋方向のSSC と言えます。
つまり「バネをためて一気に解放する」という共通の仕組みが働いています。
⚽ スポーツでの活用
-
陸上短距離:足首や下腿のStiffnessが高いと、接地時間を短くしつつ地面反力を推進力に変えられる。
-
バスケットボール:リバウンドジャンプで着地→跳躍のSSCを最大活用。
-
サッカー:切り返しやダッシュの瞬間に、股関節や膝関節のStiffnessが効く。
-
野球(投球・打撃):捻転差という回旋のSSCでパワーを爆発的に引き出す。
-
テニス・バレーボール:サーブやスパイクの踏み込み→スイングは縦と回旋のSSCが組み合わさる。
-
剣道・柔道:踏み込みや打突・投げの瞬発力もSSCの原理で説明できる。
👪 保護者の方へ
「うちの子は足が遅い」「ジャンプが弱い」――その原因は筋力不足だけではなく、Stiffness(バネの硬さ)と弾性エネルギー(SSC)の使い方にあるかもしれません。
👉 筋肉を鍛えるだけでなく、バネのように弾む力を育てることが、走力・跳躍力・投打の伸びにつながります。
✅ まとめ
-
Stiffness=バネの硬さ、弾性エネルギーを効率的に使うカギ
-
SSC=伸張→短縮でエネルギーを蓄えて解放する仕組み
-
捻転差もSSCの一種で、投球や打撃に欠かせない
-
走る・跳ぶ・投げる・打つ・切り返す――すべてにStiffnessとSSCが関与
-
野球・サッカー・陸上・バスケ・バレー・テニス・剣道・柔道など、あらゆる競技で共通する基盤
👉 PHYSICAL MONSTER ACADEMY では、SSCを上手に使えるようなトレーニングで子どもたちのパフォーマンスを最大化しています。
タグ: 柔道, 剣道, バレーボール, テニス, サッカー, 野球, 陸上, バスケ, トレーニング, ジャンプ, スポーツ